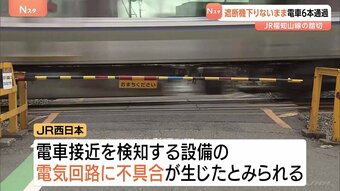昨年10月からおよそ1年間、内閣総理大臣を務めた石破茂氏の退任から1ヶ月。物価高対策、選択的夫婦別姓、戦後80年談話など在任中の取り組みと残された課題、そして退任後に急浮上した「議員定数削減」の議論や高市総理の「台湾有事」をめぐる発言など、石破前総理に在任1年と現政権の動きついて聞きました。(全2回の前編)
聞き手:荻上チキ(評論家・ラジオパーソナリティー)、南部広美(フリーランスアナウンサー)、澤田大樹(TBSラジオ国会担当記者)
(TBSラジオ『荻上チキ・Session』2025年11月13日放送「石破茂前総理がスタジオ生出演 政治とカネ、戦後80年所感…在任1年を問う」より)
在任1年の総括「集大成が戦後80年所感」
――総理を務めたこの1年間をどのように振り返り、何ができて何ができなかったと総括されていますか?
1年で全部できれば誰も苦労しません。まして少数与党でもありました。しかし、できたこともあります。例えば防災庁はまだできていませんが、その設立の流れはもう止まらないでしょう。関税交渉は、赤沢さん(経済再生相)をはじめ、みんなよくやってくれた。多くの国の中で一番いい条件で交渉できたんじゃないですかね。
それから、後戻りしそうで怖いですが、米の増産にかじを切ったのは大きかったと思っています。(大阪・関西)万博も、私が総理になった時は「絶対失敗するぜ」「赤字どうするんだ」「誰が責任取るんだ」という話でしたが、終わってみればみんなの努力で、お客様のおかげで大成功と言っていいでしょう。最低賃金の引き上げや地方創生もそうです。
結局、1年間、それぞれの大臣、それぞれの官庁、地方の方々と共に、もちろん私の能力不足はあるが、これ以上のことはできなかったよねという思いはあります。その集大成が(戦後)80年所感ということかな。
高市総理の「働いて、働いて…」発言への受け止め
――発足当初から株価が大きく変動する一方で、最低賃金の引き上げに尽力されました。日本経済にとって石破政権とはどうだったと振り返りますか?
日本経済のピークは1994年だったと思っています。GDPで18%を占めていましたが、今は4%を切ってしまっている。ドルベースで換算すると30%マイナスです。これはコストカット型の経済で、賃金が上がらず、関連会社に十分にお金が払われず、設備投資もできないからです。これではGDPが上がるはずはありません。
やはり、きちんと賃金が上がり、関連会社にお金を払い、投資にお金を使う、そういう付加価値創造型の経済に変えないと、一時期うまくいっても経済そのものは強くならない。それは華やかではないし、バーンと株価が上がったりはしません。だけども、そういう着実なものをやっていかないと、日本経済のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)は変わらない。それは着実にやれたと思っています。
――賃上げが実質賃金に追いついていくか、今が要のタイミングです。賃上げ上昇の流れを作るために、石破政権はどのような役割を果たしたとお考えですか?
2010年代だけ見ると、企業の売上は7%上がりましたが、配当や経営者の報酬は2倍以上になっているのに、賃金は3%しか上がっていません。企業は経営者と株主だけのものじゃない。そこに働く労働者、家族、地域のためのものであり、労働分配率を上げていくことは大事なことだったと思います。
ただ、防御的賃上げしかできない企業さんもたくさんあるので、そういうところにどう手当てを行うかを組み合わせる必要がありました。最低賃金の近く(の賃金)で暮らす人が700万人もいるというのはおかしいでしょう。そういう人たちは結婚に踏み切れない方も多く、お子さんもできないということが起こる。これを放置していいのかと問いたかった。最低賃金をあれだけ引き上げ、もちろん実質賃金の上昇と物価上昇の時間的ズレがあるが、着実に上がっていくことは不可逆的になったと思っています。
――高市総理は、労働規制の緩和の方向に指示を出しました。新政権のスタートをどう見ていますか?
馬車馬のように働いて、働いて、働いて、働いて、働きまくるんだと総理が決意を述べる。それはそれでいいことなのでしょう。しかし、過労死が問題になったのはついこの間の話だったじゃないですか。いわゆるブラック企業のように労働者の人権を無視するようなことが復活するということがあっちゃいけない。
また、ワークライフバランスというのは美辞麗句を言ってるわけじゃなく、きちんと確保しないと、女性の負担が過度なものになってしまう。男性の育児参加は大事なことで、ワークライフバランスを無視するようなことがあると、この少子化の構造、婚姻率が低いという構造は変わりません。最低賃金の問題も、ワークライフバランスの問題も、一体のものとして我々は進めてきました。総理の心意気と、国民全体の暮らしのあり方は、必ずしも一致するものではないと思います。