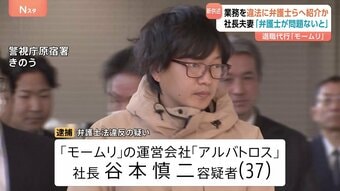今年度の最低賃金は6.0%引上げへ
こうした中で今年度の最低賃金の大幅引き上げが決まったことは、賃上げにとってはエンカレッジングなニュースでした。
国の中央最低賃金審議会は4日、今年度の最低賃金の引き上げの目安を、全国加重平均でこれまでで最も高い、63円、率にして6.0%引き上げて、全国平均で1118円とするという目安を決めました。これで、全国すべての都道府県で最低賃金が1000円を超えることになります。
最低賃金は、賃上げに対して国が直接的に関与できる、数少ない事柄であり、賃上げのモメンタムを維持することへの強い決意の表れと言えるでしょう。最低賃金の引き上げ率は、当然、働く人全体の賃上げに影響を及ぼします。
最低賃金引き上げの実施は、毎年10月からです。ちょうど、春の賃上げと、次の春闘の中間の時期にあたることから、来期の春闘、賃上げへの一つの目安になる動きです。今のようにトランプ関税の影響など先行き不透明な中で、去年を上回る最低賃金引き上げが決まったことは、それなりに大きな意味を持つものと言えるでしょう。
筒井経団連会長、賃上げに強い決意
経団連の筒井義信会長は、先日、私の単独インタビュー(『Bizスクエア』7月26日放送)に対し、「好循環の起点は、あくまで賃上げだ」と、賃上げへの強い決意を表明しました。その上で筒井会長は、「関税など不透明な状況に直面はしているが、内部留保も含めた総合体力を勘案して賃上げに取り組むべきだ」、「賃上げはコストではなく投資という位置づけで」、「物価上昇を差し引いた実質1%程度の賃金上昇を確保すべき」と語り、来年の春闘でも高い賃上げを続ける必要性を強調しました。
剣が峰に立つ「好循環」路線
政府や経済界の賃上げへの強い意志は今のところ揺らいでいません。そのこと自体は好ましいことですが、問題はそれを可能にする状況が続くかどうかです。同時に、実質賃金をプラス化するために、物価上昇を巡行速度に引き下げる政策努力が極めて重要な局面です。正直、自民党内の権力争いなどやっている暇などないはずです。
賃上げ失速リスクを回避する経済運営ができるのかどうか、この数年間の、ウクライナ危機に端を発した新インフレ時代の「好循環戦略」は、まさに剣が峰に立たされています。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)