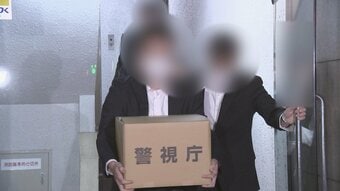今の物価高は供給要因と説明
こうした日銀の姿勢は、物価高対策に対する日銀の「冷たさ」につながっています。本来、「物価の番人」と呼ばれる中央銀行には、インフレやデフレに対応する一義的な義務があるはずです。しかし、今の日銀は、基調的な物価上昇が目標に達していないことを理由に、事実上「スルー」しています。
この点について植田総裁は、「需要からの圧力による物価上昇には利上げで対応できるが、今の物価高は供給要因なので、利上げで対応すれば、景気を冷やして所得が減る」と説明しました。供給要因インフレには利上げは直接効かない、というのです。確かに利上げをしても、コメやガソリンの価格が直接的に下がるわけではありません。
しかし、ウクライナ危機後、主に供給要因によって、アメリカで猛烈な物価上昇が起きた際、FRBは高速利上げでインフレ退治を行い、目的を成就しました。原因が、需要であれ、供給であれ、結局、インフレを抑えるには引き締めしかないという見方もできます。今の日本では、利上げを通じて為替市場の円高に寄与するのであれば、物価鎮静効果がないとは言えません。
物価高は国民の最大関心事だが
国民経済にとって、高すぎる物価上昇率は、現在、最優先の課題です。先の参議院選挙ではその民意が示されたわけです。物価高対策のために消費税減税まで議論されているのに、物価の番人である日銀が、「これは供給要因なので関係ありません」と言うのであれば、やはり違和感があります。
少なくとも、そうした説明では、金融政策を幅広い国民に理解してもらうことなどできないでしょう。難しい局面に違いありませんが、稀代の学者である植田総裁だからこそ、国民にわかるように政策を語ってもらいたいものです。
トランプ関税の企業への影響を緩和するために、再び円安になることが望ましいなどと、内心思っているのだとしたら、がっかりです。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)