◆ひと月のうちに6名の友を見送り
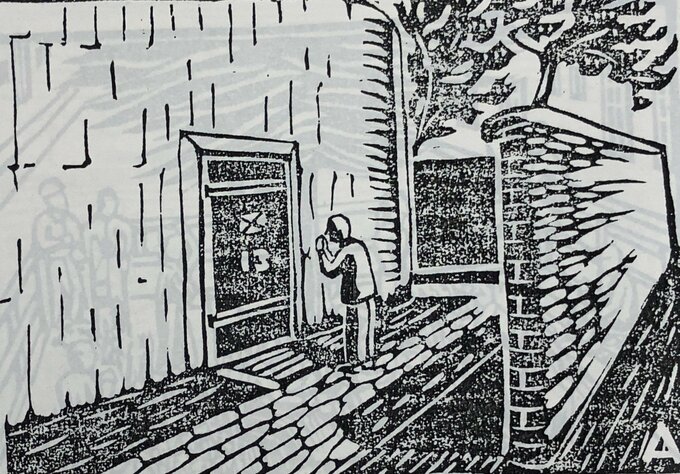
この手紙のひと月前、8月9日に松雄は母宛ての手紙を書いた。それには「お盆には総員で写真を撮って送るとの事でしたが、今日頃は写られましたやら」と写真を心待ちにしている様子が書かれていた。次々に死刑執行される仲間を見て、自分の死も迫っていると感じ、写真を早く撮ってほしいという心情を母に吐露していた。
<藤中松雄が父母に宛てた手紙 1949年9月13日付>
写真の事を書いてありましたが、実は今日ごろ届くかも知れないと心待ちにしておりましたが、「近いうちに撮って送りましょうね」と、がっかりしました。母宛ての手紙を出し、あれから六名の友が、四名と二名と二度逝かれました。既に新聞紙上で御存知の事と思います。写真の事はもう書きますまい。
スガモプリズンでは、新潟県の直江津捕虜収容所(東京捕虜収容所直江津分所)に軍属として勤務していた、柳沢章(35歳)、関原政次(36歳)、秋山米作(40歳)、小日向浩(44歳)の4人が8月19日に死刑を執行された。職業は農業や桶職人といった市井の人たちで、しかも遺書にはいずれも「捕虜を殴ってけがをさせたり死なせたりは絶対ない」と書いている。さらに4人の同僚だった鈴木賞博(33歳)と牛木栄一(54歳)は、同じ事件で、同じ日に一審と再審の判決を受けていたにも関わらず、執行は2週間後の9月3日だった。執行が遅れたことで、もしかしたら減刑になったのかもと一瞬期待させられた上で2週間を過ごした二人は「蛇の生殺しのように残されてしまい、先に死んだ人達がうらやましい」と、処刑まで寄り添った田嶋隆純教誨師に語ったという。(「わがいのち果てる日に」田嶋隆純編著)そのような6人を見送った藤中松雄は、強く自分の死を意識していた。
◆いずれ自分も逝かねばならん
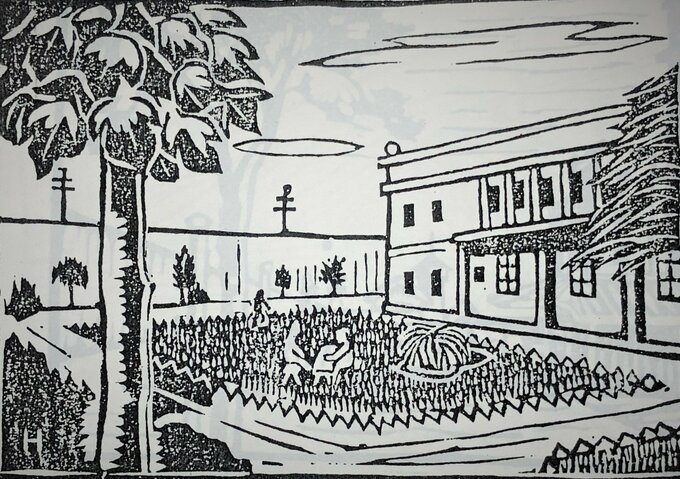
<藤中松雄が父母に宛てた手紙 1949年9月13日付>
限られた視界の中でただ生きて行くだけの生活をしている私ですが、去り行く友、或いは手紙等で知らされる知人の死を知る時、いずれ自分も逝かねばならん、その日の来るのを自覚して成佛街道を慈悲の光明に照らされて邁進致しております。光明に照らされている事は、既に御佛の慈悲によって救われている姿であります。私が救われる御仏の慈悲は私一人が救われるのではなく十方衆生、ことごとく高下貴賓の人を選ばず、みんな平等に救われるのであります。ここに他の佛と違う絶対の有難さが感じられるのです。なんと勿体ない事であり、それを思いますと、どうして感謝のお念佛となえずにおられましょうか。また、その処に悪の道を発生する余地はないのであります。
















