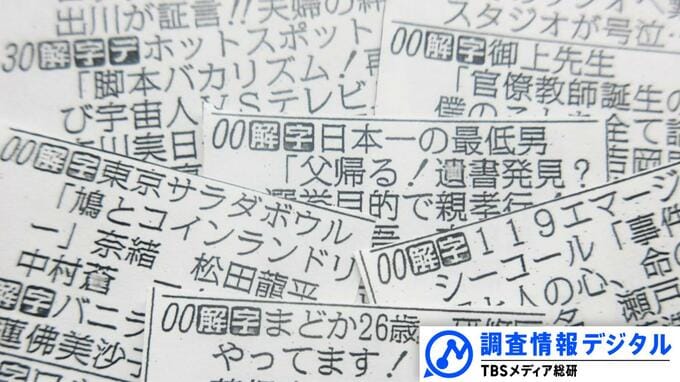2025年1月期のドラマについて、メディア論を専門とする同志社女子大学・影山貴彦教授、ドラマに強いフリーライターの田幸和歌子氏、毎日新聞学芸部の倉田陶子芸能担当デスクの3名が熱く語る。1回見逃しても全然困らないのに、なぜか毎回必ず見てしまうフシギなドラマもあって…。
バカリズムワールド炸裂!
倉田 「ホットスポット」(日テレ)はバカリズムワールド炸裂でした。東京03の角田晃広さんが宇宙人役なんですが、その荒唐無稽な設定が日常の中に普通に溶け込んでいる描写がすばらしかったですね。見ているこちらもその世界に参加している気になって「ああ、宇宙人なんだね」と素直に受け入れてしまう。もうこの世界大好き、みたいな状況になりました。
田幸 そのうちに未来人が出てきたり、超能力者が出てきたり、タイムリーパーや幽霊など、いろんなものが出てくるのに、私たちの中で「ああ、そうか」ぐらいになっている。この広い意味での多様性の描き方は、新しいドラマの表現だと思いました。
宇宙人っぽくない特徴として、超能力を使うと副作用が出るという微妙な設定も本当に上手です。頭を使う頭脳労働系だとハゲになるとか、体を使うと手足が痛くなるとか、手先を使うと指がかゆくなるとか、そういう微妙な設定がうまい。
あと、猫背。最初写真で出てきたときに、すごく猫背だな、おかしいなと思っていたら、それが宇宙人の特徴だということが後でわかる。そう思って見ていると、ホテルの業務中は、宇宙人なりにちょっと姿勢をよくしているんですね。その微妙な猫背ぐあいの調整、身体表現が本当に細かい。
バカリズムさんにインタビューしたときに、ノリみたいな感じで「宇宙人っぽくない、普通の人っぽい特徴、例えば猫背」と言ったきり、自分では忘れていたらしいんです。それなのに角田さんが、それをすごく忠実に守って、微妙な変化までつけてくれて申し訳なかったとおっしゃっていました。そのぐらい角田さんの演技と身体表現によって、微妙な宇宙人像ができていました。
うまい人ばかりなんですけれど、中でも鈴木杏さんのコメディエンヌぶり。あの淡々とした素早いツッコミは、「あっ、鈴木杏さんて、こんなにおもしろい人だったんだ」と思いました。
そして池松壮亮さんはやっぱりすごい。表情の変化だけで、考えていることが全部私たちに分かる。まるで視聴者側が超能力者になったように感情が読み取れるというのは、やっぱり彼は映像の世界の宝だなと思いました。
影山 もう一人、小日向文世さん。小日向さんが第7話の最後で、絶妙な間で「実は僕、未来人なのね」と言って、そこで第7話がスコーンと終わったでしょう。何じゃこりゃみたいに。宇宙人だけかなと思ったら、未来人だと言う。
そこから何人も、「私、超能力者よ」とか「家族も宇宙人よ」とか言い出す。本当ならば世界中がひっくり返る話ですが、最終回は「市民の過半数が知っていると言っても過言ではない。ただ不思議とその情報が県境を超えたことは一度もない」というナレーションで終わる。バカリズムの世界です。微妙な感じで本当に好きですね。
「金八先生ディスり」だけじゃない「御上先生」の大胆なチャレンジ
田幸 「御上先生」(TBS)は第1話を見た時点で、すごい作品が始まったと思いました。日曜劇場という看板枠で大胆なチャレンジをしている点にまず注目したんです。
脚本の詩森ろばさんは、もともと演劇の方ですが、映画「新聞記者」で日本アカデミー賞の優秀脚本賞を取った後に飯田和孝プロデューサーがすぐ声をかけた意欲作です。
「パーソナル・イズ・ポリティカル」、個人的なことは政治的なことだ。これは今年の流行語の一つでいいんじゃないかと思います。これは詩森さんが演劇をやる中で、ずっとベースとして描いてきたものだそうです。特別にこのドラマ用に考えていたわけではなく、ずっとやってきたものを書いたら、スタッフが「あっ、これいいね」と言って、物語の真ん中に据えたという経緯をインタビューのときに伺いました。
倉田 私も「パーソナル・イズ・ポリティカル」は心に刺さる言葉でした。学園ドラマの形をとりながら、殺人事件に発展したり、入学に関する不正が、永田町というか、政治の世界にまでつながっていくような、私たちに身近な学校という存在でさえ、政治や社会を震撼させる事件とは切り離せないという、強いメッセージ性で訴えかけてくる作品でした。
本来政治は、個人の困り事に目を向けて助けるものであるべきですが、現実は必ずしもそうではないというもどかしさを鋭く突いた作品だと思います。
椎葉さんという女の子(吉柳咲良)がフィーチャーされた回が一番心に刺さりました。生理用品を万引きして、お店から御上先生のところに連絡が来るんです。何で生理用品かというと、やはり格差が広がって、私立の学校に通っている子の中にも、生理用品を買うのに、もしかしたらお金はあるかもしれないけれども、気持ちの面で、両親がおらず、おじいちゃんが認知症というつらい境遇の中で、心の叫びがそういう形で表われる。万引きはよくないですけれど、こういった貧困が身近にあるというところが刺さりました。
このときにクラス全員の前で、御上先生が彼女に、なぜそういうことをしたのかを話させるんですけれど、それを真剣に受けとめるクラスメートの存在にも胸が熱くなりました。
私が号泣しそうになったのは、最後に御上先生が彼女のために生理用品を爆買いするんです。男の先生というところに抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、それは決して生理用品でなくてもよくて、自分は君のことをちゃんと見ている、見捨てない、その思いを伝えるのが爆買いという行動だったんだと思います。視聴者にちゃんと、こういう大人がいたら社会は安心だよねということが伝わる、一番好きな回です。
影山 御上先生を演じた松坂桃李さんはすばらしいなと思います。役の引き出しの数がすごい。松坂桃李はこんな役者だとわかったような気になっても、次の瞬間、次の作品はまったく違った角度から演じてくる。彼あっての作品だったと思います。
序盤は相当エッジが効いていて、「金八先生」をディスったあたりから、ネットも大喜びでした。でも「金八先生」のニュースだけを見た人は勘違いしたでしょうけれど、強引に言えば「御上先生」は「令和の金八先生」なんです。「金八先生」によって、その後の教員がプレッシャーを感じてきたとドラマの中で言われた。それが令和で言えば「御上先生」に置きかえられるわけです。
ものすごく頭が切れて、ツンデレじゃないけれど、実は生徒のことをめっちゃ考えている。あれが基準になったら、日本全国の教員はたまったものじゃないですよ。あれだけ生徒に寄り添うことは実際にはなかなか難しい。そういう意味では、ファンタジーなんですけれど、ファンタジーという甘さで語り切れない社会問題を大きなテーマにしたという点が、これまでの教育をテーマにしたドラマとは一味も二味も違っていたと思います。