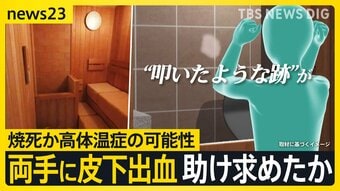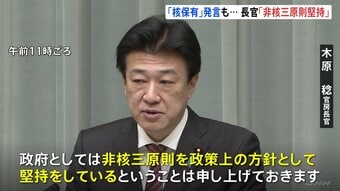様々な問題を問いかけた「最低男」
田幸 「日本一の最低男」(フジ)は間違いないと思っていました。プロデューサーが北野拓さんという30代の男性なんですが、この方はNHKの報道出身で、野木亜紀子さん作の「フェイクニュース あるいはどこか遠くの戦争の話」(NHK・2018)や、WOWOWで「フェンス」(2023)という沖縄の性暴力や地位協定をめぐるガッチリ社会派のドラマもつくった。北野さんが、民放で初めて手掛ける連ドラなので、絶対にしっかりした社会派の作品になるはずだという安心感がありました。
初回は割とポップな感じで、男性同士のケア労働を描いていました。これを、男性のプロデューサーが描くというところに既に意義があったと思っています。
さらにグリーフケアの問題が描かれています。日本人は子どもに近しい人の死の理由を教えず、死から遠ざける人が多い気がします。しかし子どもは、親が死んだのは自分のせいだと思って、自分を責めている場合がある。それに対して「あなたのせいじゃない」と言ってあげる方が、ちゃんとしたグリーフケアなんだということを描いている。
最終的には主演の香取慎吾さんが「全然最低じゃないじゃん」という声がみんなからあった。最低じゃないのに「最低男」になっている理由が最終回でわかると泣けてくるといううまさも、最後まで見てこそです。
この作品では、コンプライアンスとか、LGBT、ジェンダー、差別、障害、SDGs、働き方など、実は全てのものが描かれています。LGBTでいえば第2話で、LGBTの人たちをネタとして消費するメディアの問題を描いていました。
「御上先生」にも生理の問題が出てきましたけれど、第4話で、男しかいない家庭の中で、初潮が来た小学生の女の子が、誰にも相談できずに生理用品を万引きしてしまう。男同士のケアの中では、どうしても行き届かない部分を描く。それをサポートするのが子どもを産まない選択をする女性で、産む・産まない問題にも絡めて描いている。
すごくうまかったのが、香取さんの父親役の柄本明さんが仕事一筋で、ケア労働を全部妻と、香取さんの妹に押しつけ、そのあげく妻は逃げ、妹は病気で亡くなってしまう。これに対し香取さんは「おやじが全部押しつけてきたんだ」と断罪し、柄本さんは「自分が間違っていたなんてわかっているよ」「仕方がなかった」と言って開き直る。
そこに助け舟を出すのが、亡くなった妹の夫、香取さんの義弟の志尊淳さんなんです。「お義父さんはお義父さんの時代の価値観で生きてきただけで、それは間違っていたわけじゃない。今の僕たちが生きているこの価値観だって、後から見たら間違っているかもしれない。でも自分が生きている時代の価値観を、後から間違っていたと言われたら悲し過ぎる」と、柄本さんを肯定するんです。
社会問題を描くと、どうしても対立の図式になり、断罪することによって分断してしまう。そこを分断させずに描いた点がうまかったなと思います。
さらに、今の社会の問題の多くは、個人や家族や地域の中だけでは解決できず、結局政治の問題であり、政治を変えなければならないということで選挙の問題を描く。
それも多分5年前の価値観だったら「若い人、選挙に行こうよ」「投票率を上げよう」といった結論で終わったはずですが、今、選挙に行けばいいというシンプルな時代ではなくなっている。「オールドメディア」「既得権益」といった言葉を操り、ひどいデマや陰謀論をYouTubeでまき散らし、それを見た人達が洗脳状態でのっかり、拡散し、誰かを攻撃する。選挙のエンタメ化の問題があるわけで、5年前のように、ただ投票率を上げればいい時代から変わってきた。そういった、エンタメ化する選挙の問題点まで描いています。
この作品には今の社会の問題が、一通りパッケージとして入っていて、アップデートされた社会問題の教科書として、全ての人に見てもらいたいです。めちゃくちゃ持ち上げちゃいましたけれど。
影山 一つだけ。わからない人間に限って、タイトルにケチをつけるんですよ。というのは、僕がこれからする発言の前振りなんですけど。
「日本一の最低男」というのは、われわれにとっては、「笑っていいとも!」の有名なコーナーのタイトルですよね。金曜日に、タモリさんとさんまさんが、小さい丸テーブルを囲んで延々20分、30分しゃべる。このコーナーのタイトルが「タモリ・さんまの日本一の最低男」です。そのままなんです。
タイトルだけで語るなということを、今、僕は自戒の念を込めて言いましたけれど「日本一の最低男」というタイトルはやっぱりよくないです。田幸さんのお話を聞くにつけ、もっと違うタイトルのつけ方があったのではないか。ドラマのファンの方には申し訳ないけれど、タイトルも大事だということは言わせて頂きたいと思います。
実在の人をモデルに、震災後の福島を描く
倉田 「風のふく島」(テレ東)は、震災後の福島県に移住した実在の方々をモデルにした作品で、オムニバス形式でいろいろな方が出てきます。それぞれの思いを抱えて福島にUターンで戻ったり、結婚して住み始めたり、事業を起こしたり、ボランティアをやったりする。
ドラマチックな展開があるわけでなく、日常を優しい目線で捉えている作品です。大震災という未曽有の災害に原発事故も加わり、年月を重ねて今の福島はどうなんだろう、そこをストレートに伝えてくれる作品でした。
エンドロールで、演じた俳優さんとモデルになった方がツーショットで映るんですが、ああ、この人の物語だったんだ、この人が福島でこんなことをやって、それがこういう影響を与えているんだと感じられて、すごく好きなシーンでした。
田幸 社会問題を描いてはいるのですが、それを厳しい形で描かず、ちょっとファンタジーであり、ブラックユーモアを交えている。ウェットなもの、ストレートなものが好まれる傾向のある日本で、この作品のように、風刺のきいたブラックコメディやファンタジーのテイストで描かれる社会派ドラマというのは、もっとたくさんあっても良いのではないかと思いました。