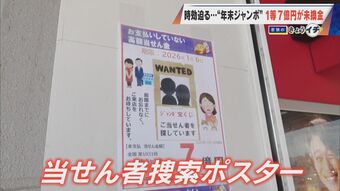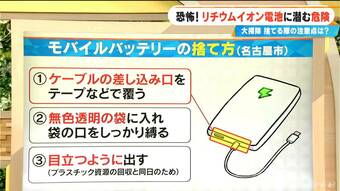江戸時代から続く消防団の存在意義に変化が…
(パトロール中の消防団)
「皆さまお出かけ前、お休み前は火の元の確認をしましょう。寝たばこ、ポイ捨ては絶対にやめましょう。」
毎月19日の「防火の日」にパトロールをするのも、業務の1つです。
(城西消防団 大橋秀雄さん(75))
「(Q:何分くらいやるんですか?)一応午後8時まで。それ以降はクレームがくるんですよ、「うるさい」って。「赤ん坊が寝れん」ってクレームがくるんですわ」

消防団の歴史は古く、
江戸時代に8代将軍吉宗が設置した「町火消」がそのルーツ。
昔は実際火事を消し止める役割を任せられていましたが、行政組織としての消防が発達した現代では…
(城西消防団 団員ら)
「(Q:ホースを握って火を消したことはある?)ない」
「私たちが行った時には火が消えている」
「消防士に「テープ貼って」と言われたり、「通行止めですよ」の呼びかけ」

現場に出動はしますが、住民の交通整理や残り火の警戒をすることが多く、消防ホースはほぼ握らないといいます。それでもいま、消防団の存在意義は逆に高まっています。
(城西消防団 水野一昭 団長)
「彼ら(消防士)だけでは無理なんです。道も動かないし、電柱も倒れるかもしれない、そんな時に私たちも手伝いができたらいいなと」