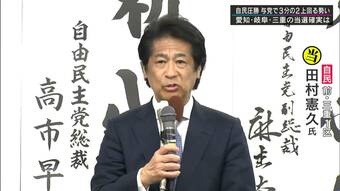津波避難タワー なぜ円柱形に?
能登半島地震でも沿岸部に押し寄せた津波。南海トラフ巨大地震で錦地区の津波到達予想は「8分後」で、逃げる時間はほとんどありません。

町は切り立った崖に避難所をつくり、どこにいても「5分以内に避難できる」状態を目指しました。こうした避難所は30か所整備されましたが、それでも高台から遠いエリアが2つ。
そこで持ち上がったのが「津波避難タワー」構想だったのです。

錦タワーの案内をお願いしたのは、町役場の小倉秀康さん。珍しい円柱形の外観には、こんな狙いが。
(大紀町役場 小倉秀康さん)
「(昭和東南地震で)流れてくる船舶が家屋を押しつぶしたことを教訓に船が当たっても丈夫なものをと考えて、円柱形の建物を建てた」

1998年に完成した「錦タワー」の総事業費は1億4000万円。いまでは最大3分の2が国から補助されますが、津波避難タワーが珍しかった当時、国の補助はゼロでした。4階までは避難所などとして使われていて、一番上の5階部分は高さが20.2メートルあります。
(大紀町役場 小倉さん)
「『一人の犠牲者も出さない』という精神のもと、全国に先駆けてタワーをつくった」
(鷺谷教授)
「タワーが(津波対策の)最初ではなく、一番最後のピース。崖づたいの避難所を整備して、それでも救いきれないところを埋める。地域のことをよく考えて計画したことが本当に伝わってくる」