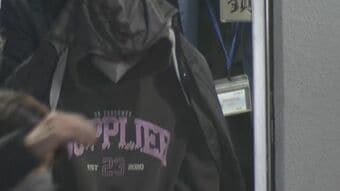SNSの伸張と放送の信頼性
2024年は、選挙イヤーだった。7月に都知事選、10月に総選挙、11月に兵庫県知事選と続いた。それらの選挙で注目されたのは、SNSの影響力である。
7月の東京都知事選では、小池百合子知事が再選されたが、2位につけたのは、予想に反して、元・安芸高田市長の石丸伸二氏だった。石丸氏は、YouTubeを使って自身の政策を主張。支援者が、それらの動画を拡散させることで、その主張が広がっていったとされる。
現職の小池都知事の対抗馬と目されていたのが、立憲民主党の蓮舫元参議院議員で、各報道機関は、この二人の一騎打ちの対決としての報道が圧倒的だった。そのことからすると、石丸氏の伸張は、既存メディアからすると想定外であったとされる。
また、自民党総裁選への出馬を断念した岸田文雄前首相に代わり、9月の自民党総裁選で、総裁に選ばれたのは、石破茂衆議院議員だった。石破首相は、総理就任早々に、衆院の解散、総選挙に打って出た。この第50回衆議院議員選挙で、新聞、放送といった伝統的メディアが争点として、連日報じたのは「裏金問題」であった。
選挙結果を見ると、自民党・公明党の政権与党は、大きく議席を減らし、過半数割れ。少数与党となったわけだが、躍進したのは、立憲民主党と国民民主党であった。特に国民民主党は、「103万円の壁」と税負担における所得制限についての主張を繰り返していた。
特に玉木雄一郎代表を筆頭に、SNSを駆使した選挙戦略を展開。これが若年層を含む有権者の支持を受けたとされる。興味深いのは、伝統的メディアが繰り返し示した争点(アジェンダ)と、有権者が関心を持った争点(アジェンダ)に乖離がなかったかという問いである。
加えて、11月の兵庫県知事選においては、伝統的メディアによる県知事選挙に対する 報道・分析と、その選挙結果との乖離が、より明確となった。今回の選挙は、現職の斎藤元彦兵庫県知事に対する不信任決議が議会で採決されたことによる失職によって行われることになった。
不信任決議の直接的な原因となったのは、斎藤知事による兵庫県庁内でのパワハラ疑惑である。この疑惑が浮上したのが、3月である。
兵庫県知事選に、失職した前知事が再出馬する事態も稀であり、また、同じく出馬した立花孝志氏が、その選挙活動中、斎藤候補を応援する活動を続けるという事態も異常と言わざるを得ない。
特に立花氏はSNS上で、事実関係を明らかにしないまま、斎藤知事の失職の原因となった内部告発者を誹謗中傷する発言を繰り返した。他方で、新聞・放送といった伝統的メディアは、立花氏のSNS上での発言は、ほぼ無視して選挙戦の模様を報じた。
神戸新聞等の調査によれば、兵庫県知事選において、SNS上でのコメントに影響を受けたとする有権者は少なくないという。ただ、このことをもって、選挙戦における「SNSの勝利」とか、「伝統的メディアの敗北」と論ずるのは早計だろう。
政治情報に関するニュース源の変化が進んでいることは確かであろう。また、エコチェンバーやフィルターバブル、アテンション・エコノミーといったSNS的な情報接触の連鎖が起こり、似たよう情報にばかり接触する状況が生まれやすいことも確かだろう。
ただ、メディア利用者がそのような状況に無抵抗というのも考えにくい。特に日本においては、伝統的メディアからの情報に対する信頼性が、一定程度担保されていることと考えあわせると、メディア利用者の姿を、SNSに容易に振り回される影響されやすい人たちという単純なオーディエンス像にしてしまうことの方が、現実を見誤るのではなかろうか。
SNS時代のオーディエンス像については、より慎重な検証が必要だが、メディア利用者に、公共性・公益性を踏まえた、より正確な情報提供の道筋を作っていくことは、民主主義という政治システムを維持、展開していくためには必要と思われる。その意味においては、ネット空間において、そのような公的な情報提供のありようも、合わせて問われていると言える。
その意味において、昨年の通常国会でNHKのインターネット業務が本来業務化され、2025年秋には、本格運用されるが、その制度整備を丁寧に検討する必要があろう。また、総務省の準備した検討の場において、インターネット空間でも、社会生活に必要な情報を情報の海に埋もれることなく的確に提供できるためのプロミネンス制度の検討も進んでいる。
2025年は、日本で放送が開始されて100年目にあたる。公共性・公益性の高い社会情報、生活情報の提供のあり方について、改めて検討されるべき時に来ているのかも知れない。
(後編の“2025年の展望”に続く)
<執筆者略歴>
音 好宏(おと・よしひろ)
上智大学新聞学科・教授
1961生。民放連研究所所員、コロンビア大学客員研究員などを経て、
2007年より現職。衆議院総務調査室客員研究員、NPO法人放送批評懇談会理事長などを務める。専門は、メディア論、情報社会論。著書に、「放送メディアの現代的展開」、「総合的戦略論ハンドブック」などがある。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。