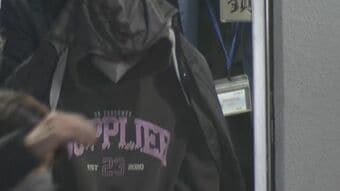メディア環境の激変で大きな転換点にある放送界。メディア論の第一人者である上智大学の音好宏教授が2024年の出来事を振り返り、さらに2025年の課題などについて展望する。前編の今回は昨年の振り返り。大谷選手に対する報道は過剰ではなかったか?選挙報道における大手メディアの信頼性は失われなかったか?放送局の人権への配慮は?
震災で幕を開けた2024年~災害報道のいま
2024年1月1日16時10分、能登半島を震源とする地震が発生。地震の規模がマグニチュード7.6、輪島市と志賀町で最大震度7を記録するという巨大地震が能登半島を襲った。最も被害の大きかった奥能登は、石川県の県庁所在地である金沢市からも交通の便が悪く、かつ、地震の影響で、道路も寸断され、救援物資を求める被災者への支援が遅れる要因となった。
元日の放送は、各局とも正月の特別編成を組んでいるが、この地震発生直後、各放送局は番組を切り替え、地震速報を伝える特別番組に切り替えていった。
NHKは、「大津波警報」が発令されたことを受け、スタジオから被災地に身を置く視聴者に避難を呼びかけるアナウンスがされたが、「可能な限り高いところへ逃げること!」「今すぐ避難! 今すぐ避難! 東日本大震災を思い出して下さい!」「一度逃げたら途中で引き返さないでください!」といった、その強い呼びかけの口調が後に「絶叫」とも表現され話題となった。
このアナウンスを行ったのは、東京アナウンス室の山内泉アナで、以前、NHK金沢にも勤務経験のある中堅アナウンサーである。
NHKアナウンス室では、2011年の東日本大震災で、津波の接近を知らせるアナウンスをしたのにもかかわらず、多くの犠牲者が出てしまった経験を受け、アナウンスにおける津波接近の呼びかけに関する抜本的な見直しの研究を始めている。
このプロジェクトでは、特に地域の特性なども踏まえたアナウンスのあり方なども検討。今回、能登半島地震発災直後に行われた避難行動を喚起する強いアナウンスは、そのような経緯のなかで準備されてきたものだった。
この「NHKアナウンサーの命を守る呼びかけ」に関する一連の取り組みは、内外から注目され、2023年度のすぐれた放送番組などを顕彰する第61回ギャラクシー賞報道活動部門で、大賞を受賞している。
他方において、大規模自然災害に向けて、放送局の壁を乗り越えての連携の可能性を探る動きも、徐々にではあるが活発化している。
災害報道に関するNHKのアナウンサーも含めた在京各局アナウンサーの勉強会の開催や、災害特番等の活用を前提に、放送局間で東日本大震災取材時の映像の交換なども行われるようになってきた。
また、愛知・岐阜・三重の3県をエリアとするCBCテレビ、東海テレビ、中京テレビ、名古屋テレビの4局は、2019年5月に「ヘリコプターの共同取材に関する覚書」を締結し、大規模自然災害発生時には、各局のヘリコプターが担う空撮映像取材の対象エリアを分担する名古屋モデルを始めた。これらの動きの背景にあるのは、その発生の可能性が囁かれている南海トラフ地震である。
また、2025年1月が、阪神淡路大震災から30年目の節目であることを意識して、2024年の春から、阪神の放送局で「民放NHK連携プロジェクト」が立ち上がり、若手記者・ディレクターを中心に、クロスロード研修といった手法などを用いながら、災害時における取材現場での具体的な対応や、その備えについての事例の共有など、局を越えて現場担当者が議論し合う連続セミナーの開催などが続いている。
大規模自然災害が発生すると、在阪局の現場記者・ディレクターは、「応援」という形で、現場の取材・応援に入ることが多い。
能登半島地震の際も、大阪局の現場記者・ディレクターが現場のデスク業務なども含め、その支援に当たった。そのような経験があるゆえに、南海トラフ地震への危機感も、よりリアリティを持って認識していると言える。日ごろ、取材競争をしている報道現場にあって、災害時に向けてこのような横連携を探る動きは、貴重な機会と言えよう。