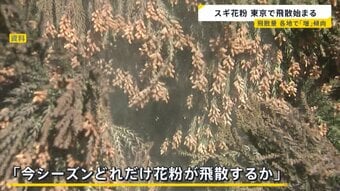争点その2・物価高対策・“年収の壁”問題など
【図表3】で「選挙期間中」にもっともテレビ報道が争点として放送しているのが「物価高」「年収の壁」「経済対策」などの「争点1」だ。最長の9時間12分を超えている。選挙期間中にこのテーマに集中して支持を訴えてSNSも駆使して結果的に議席数を4倍に増やしたのが玉木雄一郎代表(党代表の役職停止中)の率いる国民民主党だ。
【図表5】で自民党の石破茂総裁、立憲民主党の野田佳彦代表、国民民主党の玉木代表の3者で「選挙期間前」「選挙期間中」「投開票日以後」の12日間で比較してみると、「投開票日以後」で玉木氏の放送時間が野党第一党の立憲民主党の野田代表に迫る長さであることが注目に値する。
通常は各党首のテレビ報道における登場時間は、与党第一党の党首(通常は総理)が最長で、次に野党第一党の党首となるのが選挙報道ではお決まりのパターンだ。野党第三党である国民民主党の玉木氏が「投開票日以後」に立憲民主党の野田代表に迫る放送時間を記録しているのは異例ともいえる状況だ。
選挙の後で、過半数割れした与党側が個々の野党に対して争点ごとに協力をあおぐかたちで国会運営を進めざるを得なくなった。そうした中で、「争点1」で「103万円の壁」の撤廃を主張して有権者の支持を集めた玉木代表が選挙後に壁撤廃をめぐって自民党や立憲主民党などと交渉する様子がニュースの中でもたびたび報じられるようになり、テレビ報道でも露出が増えていた。
少数与党に転落した自民党としては法案や予算案を通すのに野党の一部の賛成を取り付ける必要がある。このため衆院選後の政策のキャスティングボートを国民民主党が握った格好になっている。玉木氏が選挙期間中から主張していた「103万円の壁」の撤廃が与党との協議で実現する方向へと進んでいる。玉木氏の放送時間の急増はそうした表れと分析することができる。

そのほかのトピックで見てみると、【図表3】を見る限り、「選挙期間中」には、日本という国にとって喫緊の課題である「争点3」(少子化対策)、「争点5」(地方創生・防災対策)、「争点6」(選択的夫婦別姓)、「争点7」(原発回帰など)、「争点8」(憲法改正)などにテレビ報道が十分に時間をかけているとは必ずしも言い難い。