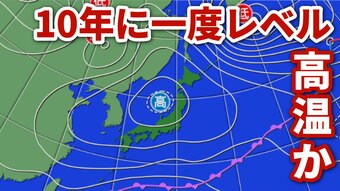“暴力の容認”とメディア、次世代への想い
保阪さんは、日本が戦争に向かった背景について、「社会が暴力を容認したこと」を大きな要因として挙げた。

犬養毅首相が青年将校に暗殺された五・一五事件から、首相官邸が襲撃された二・二六事件までの間に、テロやクーデターが相次いで起きた。すると、国民は疲弊した農民を救って権力の象徴を打倒すると訴えた将校らの動機に同情し、減刑を求める嘆願運動を起こした。
戦場体験者(沈黙の記録より)
「『動機が正しければ道理に反することも仕方ない』という論調が出来上がっていった。日本国中に異様な空気が生まれていったのである」
その暴力を容認する空気を後押ししたのが、他ならぬメディアだった。

保阪正康さん
「一生懸命、万歳万歳ってかくわけですよ。売上部数が伸びるわけですね。『新聞は商品である』と、ある経営者が言ったけど、まさにそうなんです。メディアの中で飯を食うということは、新聞記者は国策に協力しなければ記事が書けない」
――戦中の太鼓を叩いたジャーナリストたちの行動がビジネス的には正しいものになってしまう状況が、今の日本のメディアの状況のようにも思うのですが
保阪正康さん
「主体性や会社の性格は、今はあまりないんじゃないかと思う。みんな戦う同志なんですね。業界全体があまりよくないと、村になっていくんだなと思います」
8月7日、都内で行われた「“新しい戦前”にしないために」と題された講演会。

保阪正康さん
「具体的にどういう仕組みで戦争になったのかということを日本は検証してない。教訓化していくことで私たち自身が変わるんですね」
保阪さんのメッセージは若者にどのように伝わったのか。
参加者
「人と人が向き合うっていうのもそうだし、過去あったことと向き合うというのもやらないといけないと思います」
「何かおかしいと感じたら声をあげるのも大事だし、自分の思うことをつぶさないでほしい」
保阪さんは次世代への想いをこう記している。
戦場体験者(沈黙の記録より)
「最終的に私が辿りついたのは、つまるところ次の信念であった。<記憶を父とし、記録を母として、教訓(あるいは知恵)という子を生み、そして育てて次代に託していく。>」