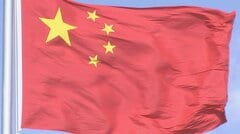ナイトタイムエコノミーと労働
前述したように、深夜営業が難しくなった背景には、人件費の増大や人材確保の困難さがある。
深夜労働は、雇用する側にとっては明確なコストであり、店舗運営の合理性という点では見直しの対象になりやすい。
一方で、夜の街や深夜営業の店舗、長時間滞在が可能な空間は、本来、誰かを支援したり居場所を提供したりする目的で設計された場所ではない。
それにもかかわらず、結果として、行政サービスや家族、地域コミュニティといった既存の受け皿では対応しきれない人々や、ただ「居場所が欲しい」人々を、黙って引き受けてきた。
しかし、この機能は商業空間としては極めて不安定である。
オールで滞在してもコーヒー一杯しか注文されなければ、採算は取れない。
彼らの目的は商品や食事の消費ではなく、「場所にとどまること」そのものだからである。
こうした利用のされ方は、店舗側の想定から外れやすく、その結果、滞在者は「邪魔」「居座り」「回転率を下げる存在」として語られてしまう。
一方で、夜間営業を行う店舗が減ることは、働き方の選択肢も消しつつもある。
夜に店が開いていないということは、単に利用者の利便性が下がるという話ではない。
あえて夜の時間帯に働くことで生活を成り立たせてきた人々にとって、その働き方自体が成り立たなくなりつつあることを意味している。
かつては存在していた「時間帯を選ぶ余地」が、社会の合理化や効率化の流れの中で、一方向に削られているのである。
夜に働くことができた人々にとって、その選択肢が失われることは、働き方の自由が狭まることに直結する。
昼間の労働に困難を抱える人々にとって、深夜に働くという選択は、社会から離脱することではなかった。
むしろそれは、昼の規範から一時的に距離を取りながら、社会とのつながりを保つための現実的な逃げ道として機能してきた。
夜の公共性は、そうした回避や調整を受け止めることで、人を社会の外へ押し出すのではなく、かろうじて内側につなぎとめる役割を果たしてきたのである。
この意味で、夜の公共性は外部から一方的に与えられる保護ではない。
そこに身を置き、働き、夜の街を支えることで、初めて当事者自身の公共性として成立してきた。
彼らは夜の公共性に守られる存在であると同時に、その公共性を成り立たせてきた担い手でもあった。
商業空間が代替してきた「居場所」の行方
カフェやファストフード店、カラオケ、ネットカフェといった空間は、本来、飲食や娯楽といった「商」としての利用を前提に設計されている。
しかし実際には、運営側が意図していないかたちで、人が長時間滞在し、身を落ち着け、ただ時間をやり過ごすための場所としても機能してきた。
そこにいたのは必ずしも「消費」を目的とする人だけではない。
家に帰れない、帰りたくない、あるいは一人になりきれない人が、理由を問われず身を置くための受け皿として、制度的な設計とは無関係に、夜の公共性として成立してきた。
しかし、営業時間の短縮や交通機関の削減とともに、こうした空間は静かに消え始めている。
その結果、深夜に働く人と、夜に居場所を必要とする人の双方が、同時に行き場を失いつつある。その影響はすぐには可視化されないが、孤立や不調として個人の内側に蓄積され、後になって社会問題として現れるのかもしれない。
だからこそ問われるべきなのは、「夜を元に戻すかどうか」ではない。
夜が担ってきたこうした機能を、都市の中でどのように位置づけ、誰がそのコストを引き受けるのかである。
ナイトタイムエコノミーは、単なる経済の問題ではなく、都市が人をどう包摂するかという公共性の設計課題として捉え直されるべきだろう。
問題視されるべきなのは、夜に滞在する人そのものではない。
本来は社会全体で共有されるべき機能が、見えないまま特定の場所や人々に委ねられてきた、その構造こそが問われているのである。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 研究員 廣瀬 涼)