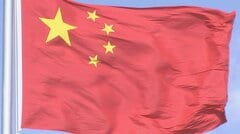夜の公共性
さて、このナイトタイムエコノミー、それは単なる消費や雇用の問題に還元されるものではない。むしろ、都市における「夜(非制度的な)の公共性」を下支えしてきた社会的装置として理解される必要があると筆者は考える。
一般に公共性とは、特定の人や集団だけのものではなく、誰に対しても開かれ、利用する理由や立場を問われない性質を指す。
役所や公園など、国家や自治体が整備する公共施設は、その代表的な例であり、公共性はしばしば私的な領域と対比されるかたちで、社会の共通基盤として理解されてきた。
ただし、公共性は必ずしも制度として明確に設計された空間だけに存在するわけではない。
実際の社会では、人々が互いの存在を感じながら過ごし、完全に私的でも、完全に制度的でもない「中間的な場」においても公共性は成立してきた。
そうした場では、誰かに属しているかどうかや、明確な目的を持っているかどうかが厳密に問われることなく、人がそこに居ること自体が許されているのである。
夜の公共性とは、夜という時間帯に、特定の所属や目的を持たなくても、人が一時的に身を置くことを許される「ひらかれた場」や状態を指す。
それは、役所や公園のように制度として設計された公共空間だけを意味するものではない。
むしろ、深夜まで開いているカフェやファミリーレストラン、24時間営業のコンビニ、終電後も動く交通機関、夜遅くまで人の気配が残る街路といった、完全に私的でも完全に制度的でもない場所や機能によって支えられてきた。
昼の公共性が、仕事や学校、用事といった目的や役割を前提に成り立っているのに対し、夜の公共性には異なる性質があった。
夜には、何をしているのかを説明する必要も、どこかに所属している必要もなく、ただ「そこにいていい」という状態が許されていた。
言い換えれば、夜の公共性とは、「何者でもないまま存在すること」が認められる公共性だったのである。
単なる消費の場ではなく、家庭や職場といった強い役割や規範から一時的に距離を取りたい人を受け止める「緩衝地帯」として機能してきた。
多くの人にとって、仕事や学校を中心とした昼の時間帯が生活のスタンダードになっているとすれば、夜の街は、その標準的な時間軸から一時的に外れることが許される場だった。
そこでは、社会から完全に離脱する必要も、日中と同じ役割を引きずり続ける必要もなかった。そのような中間的な状態が、夜には許されていたのである。
夜に街を歩いたり、店に身を置いたりすることは、単なる現実逃避ではない。
昼間に担っていた役割をいったん中断し、気持ちを整えながら、再び日常へ戻るための準備をする時間でもあった。
だからこそ、筆者が感じたような非日常性や、「夜だから」という理由で少し羽目を外してしまう感覚が生まれていたのだろう。
ナイトタイムエコノミーの縮小は、単に夜間の経済活動が減っているという問題ではなく、都市の中で「緩衝地帯」として機能してきた公共空間が後退していることを意味している。
深夜営業の店舗や交通機関が減少することで、夜は「誰もが一時的に滞留できる時間」から、「帰属先に戻るための時間」へと性質を変えつつある。
読者にとってこの問題を身近に感じるとすれば、たとえば「終電を逃したら、ファミレスやファストフード店で始発まで待つ」という選択肢が、もはや現実的ではなくなりつつある、という点にあるだろう。
深夜まで開いている店が減った現在、夜をやり過ごすための物理的な場所そのものが失われている。
あるいは、失恋して誰かに話を聞いてほしくなり、「とりあえずファミレスに集合しよう」と声をかける。
かつてのドラマや漫画では当たり前のように描かれてきた、そんなワンシーンですら、夜の公共性が後退することで成立しにくくなっている。
夜に集まり、話し、気持ちが落ち着くまで時間を共有するための「場」が、もはや自明には存在しないからだ。
夜の公共性の後退とは、特別な人だけが困る話ではない。
誰もが一度は経験したことのある、あるいは経験しうるはずだった夜の過ごし方が、静かに選択肢から消えていくことを意味しているのである。
筆者が深夜に行き場を失い、街から静かに押し出されるような感覚を覚えたのは、単なる個人的な判断ミスではない。
夜の公共性が後退しつつある状況を、身体的に経験した出来事だったと捉えることができる。
セルフケア/シェルターとしての「夜の公共性」
夜の公共性は、制度化されていないセルフケアの場として機能してきた。
公式な支援に接続される以前に、人が自分を保ち直すための、きわめて日常的で初期的な自己調整の空間である。
セルフケアという言葉からは、カウンセリングや医療、休養、メンタルヘルスといった、意識的で制度的なケアが想起されがちである。
しかし、夜の公共性が担っていたのは、そうした支援に至る以前の段階だった。
家に帰らないという選択をすること、誰とも深く関わらずに人の気配の中に身を置くこと、何かを達成するでも消費するでもない時間をやり過ごすこと。
これらは、「限界に近いが、まだ助けを求めるほどではない」状態にある人が、自分を壊さずに保つためのセルフケアだった。
その結果として、夜の公共性はシェルター的な役割も果たしていた。
ただしそれは、生活困窮者向け施設や避難所のような公式なシェルターではない。
「ここにいてもいい」「今すぐ決断しなくていい」という状態を一時的に保証する、非公式で曖昧な避難先である。
家にも職場にも戻れず、しかし完全に孤立したくはない人が、深夜営業のカフェやファミリーレストラン、コンビニ、夜の街路、深夜バスに身を預けていた。
DVや家庭内トラブル、衝動的な家出といった状況においても、一時的な緊張から距離を取るために、ただ「今夜をやり過ごす」ことを可能にする場として機能してきた。
そこは、助けを求める決断を下す前に、まず逃げることだけを許してくれる場所であり、身体的な安全と時間的な猶予が確保される空間でもあった。
夜の公共性は、支援や宿泊を提供する場ではなく、社会的役割から一時的に距離を取り、自分を立て直すための余白として機能してきたのである。
夜の公共性の後退とは、夜間の経済活動が縮小したという事実以上に、都市が人を一時的に受け止めるために持っていた余白が失われていることを意味する。
そこでは、理由を問われずに身を置き、自分を立て直すための時間が確保されてきた。夜の公共性は、支援と孤立のあいだに存在する非公式な受け皿であり、その喪失は、個人の困難を見えにくいかたちで深刻化させる。
したがって、ナイトタイムエコノミーは経済の問題であると同時に、都市の包摂機能をどう維持するかという公共性の課題として捉え直される必要がある。