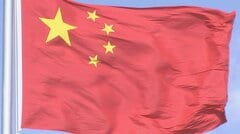深夜に街を彷徨う、という個人的な体験を手がかりに、近年進行するナイトタイムエコノミーの縮小が、都市における「夜の公共性」にどのような影響を及ぼしているのかを考察する。
夜間営業の飲食店や交通機関の減少は、しばしば人手不足や合理化の問題として語られるが、ここではそれを単なる経済現象としてではなく、人が理由を問われずに身を置くことのできた時間と空間の後退として捉える。
夜の街は、家庭や職場といった強い役割から一時的に距離を取り、社会との接続を完全には断たずに自分を保ち直すための余白として機能してきた。
そこは制度化された支援でも私的な空間でもない、非公式で中間的な公共性が成立する場であった。
しかし、深夜営業の縮小や交通インフラの再編によって、こうした場は静かに姿を消しつつある。
ここでは、夜の公共性を、制度化されていないセルフケアや緩やかなシェルターとして位置づけ、ナイトタイムエコノミーを、経済の問題であると同時に、都市が人をどのように受け止めてきたのかという公共性の設計課題として捉え直すことを試みる。
年末、彷徨う、、、
年末、些細なことで家族と口論になり、23時過ぎに家を飛び出した。
感情の行き場を失ったまま外に出るという行為に、特別な目的や計画はなかった。
学生時代から深夜までアルバイトをしたり、オールで遊ぶことも珍しくなかったため、夜中に外出すること自体に心理的な抵抗はほとんどない。
意味もなく電車に乗り込み、いっそ夜行バスで地元に帰ってしまおうかと車内で時刻表を調べた。
すると、かつて確かに存在していたはずの地元行きの夜行バスが、すでに運行を終了していることに気づく。
新幹線や在来線の終電も当然ながら終わっていた。
選択肢を失い、仕方なく終点で一度降り、反対方向の電車に乗り換えて最寄り駅へと引き返すことになった。
最寄り駅に着いたのは深夜0時前後だった。
朝までカフェで時間を潰そうと思い立ち、スマートフォンで周辺を検索する。
しかし、開いている店が見当たらない。
カフェはもちろん、ファミリーレストランもファストフード店も閉まっている。
年末年始だから、という一言では片づけられない数の「営業終了」が画面に並んでいた。
私が大学生だった十数年前、深夜の飲食店は決して特別な存在ではなかった。
夜な夜なカフェやファミレスに集まり、取り留めもない話を延々と続ける。
テスト期間には終電を気にすることなく居座り、眠気と戦いながら教科書を開く学生の姿があった。
そうした光景は、「日常」だったはずだ。
しかし現在、深夜営業は明らかに縮小している。
チェーンの居酒屋ですら、朝方まで営業する店舗は目に見えて減った。
コロナ禍以降に深夜営業の店が縮小したという話は耳にしていたがコロナ収束から数年が経ち、しかもここは都内である。
正直なところ、「夜の東京」はもう元に戻っているものだと、私は無意識に思い込んでいた。
仕方なく、温かい飲み物でも買って散歩をしようと考え、コンビニに立ち寄ろうとした。
しかし、そのコンビニも営業していなかった。
その瞬間になってようやく、自分が夜中に家を飛び出したという行為の無謀さを実感し始める。
それでもなお、「都内なのだから、どこかしら開いているはずだ」という感覚が、最後まで私の判断を鈍らせていたのも事実だった。
夜中に出歩かなくなってから、気づけば数年が経っていた。
その間に、私の中の「夜の街」のイメージは、いつの間にか過去のまま固定されていたのだろう。
学生時代に夜中を自由に過ごせたのは、単に時間を持て余していたからではない。
その時間に起きていても問題がない、つまり社会的な責任をまだ大きく負っていない立場だったから可能だったのだ。
そして、あえて深夜に活動するという行為には、日中とは異なる背徳感があり、その感覚自体が高揚感を生んでいた。
だが、その背徳感は、誰かの労働の上に成り立っていた。
深夜に店を開け、電車を動かし、街の機能を維持する人々がいたからこそ、「夜」は居場所として成立していた。
その前提が崩れつつある現在、夜が静まり返るのは、ある意味で必然なのかもしれない。
ナイトタイムエコノミー
この体験は、ナイトタイムエコノミーが一部で回復や再編を見せている一方で、深夜営業の短縮や交通機関の削減が示すように、夜に利用できる場所や時間が以前に比べて明らかに縮小していることを、身をもって実感させるものだった。
ナイトタイムエコノミーとは、主に18時から翌朝6時頃までの時間帯に営まれる経済活動全般を指す言葉である。
レストランや居酒屋、バーといった飲食店をはじめ、ライブハウスやクラブなどのエンターテインメント施設、さらにはジムの利用や映画鑑賞といった夜間の余暇活動も含まれる。
加えて、これらの活動を支える電車やバス、タクシーなどの交通サービスも、ナイトタイムエコノミーを構成する重要な要素である。
新型コロナウイルス感染症の拡大は、人々の外出行動そのものを大きく制限した。
不要不急の外出自粛や三密回避、いわゆる「ステイホーム」が社会的要請として広がり、夜間を含めて外に出かけることが難しい状況が続いた。
特に「三密」の対象とされた居酒屋をはじめとする飲食店では、営業時間の短縮や休業要請が繰り返され、夜の街から人の流れが急速に失われていった。
人々が外出できない以上、夜間の需要そのものが消失し、都市のナイトタイムエコノミーは大きな打撃を受けた。
こうした状況は飲食店にとどまらず、コンビニエンスストアなど他の業態にも波及した。
日本経済新聞の調査によると、2019年10月から2020年2月までの約4カ月間で、セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンの大手3チェーンにおいて、400店超が24時間営業を終了した。
特徴的なのは、時短営業に切り替えた店舗の多くが大都市圏に集中していた点である。
全体の約6割が札幌、東京、名古屋、大阪、広島、福岡といった主要都市圏に立地し、その大半は都心部ではなく郊外エリアだった。
商圏に一定の人口がある地域であっても、深夜帯の人手不足により24時間営業を維持できない店舗が増えていたことがわかる。
なお、日本経済新聞社が2019年5月に実施した調査では、コンビニエンスストアの24時間営業の見直しについて、「賛成」と回答した人が41.1%、「どちらかというと賛成」が31.5%にのぼった。
両者を合わせると、消費者の72.6%が24時間営業の見直しに肯定的な姿勢を示しており、深夜営業の縮小は事業者側だけでなく、利用者側にも一定程度受け入れられていたことがうかがえる。
また、JR東日本は2020年10月、山手線を含む17線区で終電の繰り上げを発表し、JR西日本も2021年3月から近畿エリアの主要線区において10〜30分程度の終電繰り上げを実施している。
これにより、都心から住宅地へ帰ることのできる時間的余地は確実に縮小した。
深夜帯の移動を支えてきた公共交通機関でも、夜間サービスの縮小は進んだ。
東急バスは2022年7月、渋谷駅から溝の口、宮前平、青葉台、仲町台、新横浜方面へ運行していた深夜急行バス「ミッドナイトアロー」を廃止した。
かつては終電後の帰宅手段として機能していた路線だが、再開されることなく姿を消した。
こうした交通インフラの変化は、夜間の外出行動そのものに影響を及ぼしている。
終電が早まれば、外食や飲酒、深夜の滞在といった行動は成立しにくくなり、結果として居酒屋などの閉店時間も前倒しされやすくなる。
実際、夜の飲食店が以前より早く閉まるようになった背景には、人手不足によるアルバイト確保の難しさとあわせて、こうした構造的な制約が重なっていると考えられる。
さて、コロナ禍が落ち着き、いわゆるアフターコロナの段階に入った現在、表面的には徐々に以前の生活を取り戻しつつある。
しかし、すべてが元に戻ったわけではない。
外出制限や営業自粛といった強制的な制約は解除されたものの、コロナ禍の中で定着した生活様式や行動パターンは、そのまま残り続けている。
2024年4月に共同通信が実施した調査によると、コンビニエンスストア主要6社において、24時間営業を行っていない時短店舗は約6,400店に上り、全体の1割を超えている。
調査時点で6社が国内に展開する店舗数は計約5万5,500店であり、深夜営業を縮小する動きが業界全体に広がっていることが明らかになった。
最大手のセブンイレブンでは、加盟店の希望による時短営業店舗が2020年度と比べて200店以上増加し、ローソンでも約100店増えている。
こうした背景には、人手不足だけでなく、都心部に特有の人口構造がある。
日経クロストレンド(2023年8月3日)によれば、国勢調査に基づく千代田区の昼夜間人口比率は約1750と突出しており、夜間人口は昼間人口の約17分の1にまで減少する。
日中は通勤・通学者で賑わう一方、夜間や週末には人が急減するため、深夜帯の消費需要そのものが成立しにくい構造となっている。
このような環境では、フランチャイズ加盟店にとって24時間営業は採算面・人員面の両面で大きな負担となりやすく、結果として深夜営業の見直しが進んでいると考えられる。
さらに、この構造的な変化を後押ししたのが、コロナ禍を通じて共有された生活経験である。
外出自粛や営業時間短縮が続く中で、夜遅くまで営業する店や24時間稼働するサービスがなくても、生活は意外と成り立ち、日常が致命的に崩れることはなかった。
「以前は不可欠だと考えられていたものが、なくても案外なんとかなった」という実感が、多くの人に共有されたのである。
その結果、夜間の外出や深夜営業は、「制限されているから行われない」のではなく、「なくても困らないもの」として優先順位を下げられるようになった。
コロナ禍は一時的な非常事態であると同時に、私たちの生活や都市のあり方を試し直す実験期間でもあり、その過程で、夜をめぐる新たな基準や前提が静かに形成されたと考えられる。