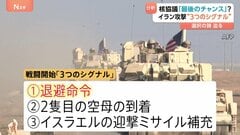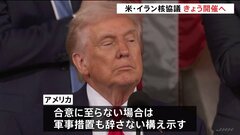5|デジタル娯楽~物価高でも抑制対象ではない、デジタルコンテンツは生活に定着
電子書籍や音楽・映像・ゲームソフトといったデジタルコンテンツに対する支出額は、コロナ禍による一時的な増減を経ながらも、前年と同様、あるいは上回る水準で推移している。特に足元では「DL版の音楽・映像、アプリなど」の増加率が高い。
これらの数値は名目値であるため、実質ベースでは物価上昇の影響を受けている可能性がある。それでも、支出額はおおむね維持されており、足元では増加も見られる点は注目に値する。
「電子書籍」は足元でやや弱含む動きも見られるが、インターネット上には無料コンテンツや低価格の代替サービスが数多く存在する中でも、消費者は一定の支出を維持している。
こうした傾向は、デジタルコンテンツが生活の中で不可欠な価値を持つものとして定着していることの表れと言える。
物価高により生活必需品への支出を抑制する中でも、デジタル娯楽への支出は維持されている。
比較的低価格でアクセスできるデジタルコンテンツは、コストパフォーマンスの高い娯楽として位置づけられ、「メリハリ消費」において優先順位の高い分野となっている様子がうかがえる。
おわりに~実質賃金マイナス下でも、慎重さの中にある前向きな変化に注目
本稿では、総務省「家計調査」を用いて、2025年9月までの二人以上世帯の消費動向を分析した。
その結果、実質賃金がマイナス圏を推移する中で、物価高によって培われた消費者の慎重な行動パターンは継続しており、食料や日用品などの生活必需品に対する支出を抑える一方で、娯楽に対しては一定の支出を維持する「メリハリ消費」の動きが確認された。
一方で、8・9月にかけては「教養娯楽」や「食料」の支出が改善傾向を見せるなど、慎重な消費姿勢の中にも生活全体を整え直そうとする動きの兆しも見える。
実質賃金の改善が直ちに全般的な消費拡大につながるわけではないが、娯楽関連支出の一層の回復や、これまで抑制してきた生活必需品の支出水準の緩やかな正常化といった変化が、実質賃金がマイナス圏にある中でも表れ始めているのかもしれない。
分野別に見ると、旅行分野では「パック旅行費」が8・9月に前年比+70%前後と大幅に増加した。
円安への心理的順応に加え、燃油サーチャージ込みの定額プランなど費用感を把握しやすい商品が増えたことや、インバウンド需要との競合を踏まえた「早めの予約」といった合理的な行動が広がったことが背景にあげられる。
海外旅行の伸びが特に顕著であり、為替の不安よりも旅行機会を重視する意識の変化が見てとれる。
交通分野では、公共交通機関の利用が持ち直す一方で、レンタカー・カーシェアリングはやや落ち着きが見られる。パック旅行の急増により、観光需要が団体・パッケージ型へと移行し、個別移動ニーズがやや弱まった可能性がある。
食事分野では、外食需要は引き続き堅調だが、飲酒代は6月以降前年を下回っており、猛暑や健康志向の高まりを背景に飲酒頻度を減らす動きが広がっている可能性がある。
内食では、米という基本的な主食でさえも価格上昇により買い控えが生じる一方で(9月は反転)、冷凍調理食品や出前などの利便性重視の食品・サービスは堅調を維持している。
この対比は、消費者が価格と利便性の両面で厳しく選択を行っていることを示すとともに、物価高の中で日常の基本さえも見直さざるを得ない現実を浮き彫りにしている。
デジタルコンテンツへの支出も堅調であり、無料や低価格の代替手段が豊富にある中でも一定の対価を支払って楽しむ行動が根付いている。これは、コストパフォーマンスの高い娯楽として、物価高の中でも優先順位の高い支出となっていることを示している。
総じて、実質賃金がマイナス圏にある中でも、消費者の行動には「メリハリ消費」を基調としつつ、長期にわたる節約から生活を少しずつ整え直そうとする前向きな変化の兆しもあるようだ。
成熟した消費社会では、すでに安価で高品質な商品やサービスが多く流通しており、購買力の回復が直ちに全般的な消費拡大につながるとは限らない。
それでも、実質賃金の改善が持続すれば、特に娯楽や利便性の高いサービスなど「メリハリ消費」において優先順位の高い分野を中心に、消費全体が少しずつ前向きな方向に動き出すことが期待される。
今後は、消費者の慎重さの中にある価値観に基づく選択的な消費回復の動きが注目される。
※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 上席研究員 久我 尚子
※なお、記事内の「図表」と「注釈」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。