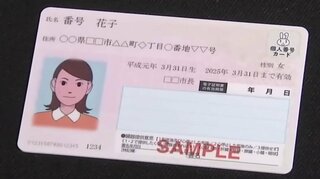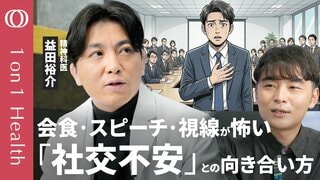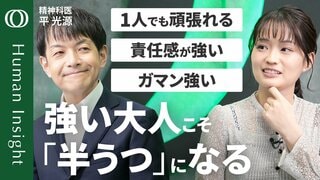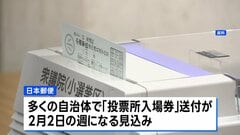「悪い薬物はなく、悪い使い方だけがある」 薬物依存症の背景にある社会的課題
薬物問題を考える上で重要なのは、薬物そのものを悪者にするのではなく、その使い方や依存にいたる背景を理解することだと松本医師は強調します。
中でも市販薬依存の問題が若年層で急増している現状についても触れています。
「2024年は市販薬依存が劇的に増えていて、10代の薬物依存症患者の7割以上が市販薬の依存症です。特に女性が多いんです」
日本では国の政策として市販薬の利用を促進してきた歴史があり、ドラッグストアの増加とともに市販薬へのアクセスが容易になっています。
薬物の規制が進む一方で、若者たちは規制対象外の薬に手を出すという「モグラ叩き」のような状況が生じています。
松本医師は薬物依存の背景には様々な社会的・個人的要因があると指摘し、薬物規制だけでなく、使用者への支援も重要だと訴えます。
「薬物依存症の臨床現場で見ていると、虐待を受けている方やいじめを受けている方が多いです。精神疾患を持っている方も多いですし、非常に才能があって大きなプレッシャーを抱えている方、発達障害や知的ハンディキャップがあって器用に生きられない方もいます。薬物にはまってしまう方たちは、そうでない方よりもいろんなハンディを背負っています。薬物問題の対策は、薬というものの対策にばかり集中して、痛みを抱えている人の支援、人間の対策が全然放置されています。これがこれまでの薬物対策全般の課題だと思います」
松本医師は「悪い薬物」と「良い薬物」の区別よりも、「良い使い方」と「悪い使い方」があると考えています。
薬物に依存している人を人格否定するのではなく、なぜその人に薬物が必要なのかを考え、背景を考える視線を持つことが大切だと話します。
「薬物を使っている人を『ダメな人』と人格否定するのではなく、なぜこの人はタバコが必要なのだろう、なぜお酒を飲みすぎてしまうのだろうと考えることが大切です。少しずつ優しい視線を持つことで、これまで自分でじっと耐えてお酒やタバコで我慢してきた方たちが、普通に誰かに相談したり、本質的な困りごとを言い出しやすい社会になっていくのではないかと考えています」
さらに、薬物を囲んで人々が集まり、コミュニティを形成するという正の側面も指摘します。
喫煙所で重要な会話が交わされたり、パーティーの中心よりも喫煙所に集まった人たちの方が楽しい会話が生まれることもあるといいます。
「お茶でもお酒でもタバコでも、それを囲んで集う人たちにできる結びつきがあります。なんでもかんでもダメというのではなく、安全にコミュニティにつながるような形で付き合えるスペースや空間を作ることはできないかと思います」
身近な薬物との適切な距離感を模索する
アルコール、カフェイン、ニコチンという私たちの身近にある「ビッグスリー」の薬物は、それぞれ異なる作用と歴史を持ちながら、人類の発展に大きく寄与してきました。一方で、健康被害や社会問題の原因にもなっています。
松本医師の解説では、これらの薬物を一律に「悪」とするのではなく、その複雑な側面を理解した上で、適切な付き合い方を模索することの重要性が見えてきます。
アルコールについては、健康リスクを考慮した適量の摂取(日本酒で1日1合未満)、カフェインは500mg(コーヒー約5杯分)を超えないようにし、時には摂取しない日を作ってリセットすることが勧められています。タバコについては、他者に迷惑をかけない形での使用を模索しつつ、喫煙者の存在を否定しない配慮も必要だと松本医師は提案しています。
大切なのは、薬物依存の背景にある社会的・個人的な課題に目を向け、依存している人たちへの支援の充実です。
私たちの身近にある「ビッグスリー」の薬物も、使い方次第で人生を豊かにも、逆に苦しみをもたらすこともあります。
大切なのは、これらの薬物の性質をよく理解し、適切な量と適切な場所で使うこと、そして何より、薬物に頼らなくても困難を乗り越えられる人間関係や社会的サポートを築くことなのかもしれません。
※この記事は6月1日にTBS CROSS DIG with Bloombergで配信した「Human Insight」の内容を抜粋したものです。