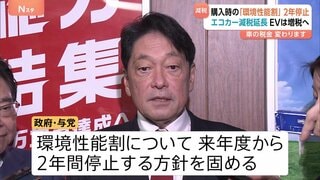他の主食で代替、安価な銘柄の選択、価格高騰にどう対応?
消費者が直接支払うコメの店頭価格の変動は、私たちの毎日の食生活や家計に大きな影響を及ぼす。
店頭価格が上昇すれば、当然ながら家計における食費の負担は重くなる。特に、コメを主食とし、毎日消費する家庭にとっては影響が大きい。
標準シナリオでもじわりとした負担増が続き、高騰シナリオに至っては、他の支出を切り詰めてでもコメ代を捻出しなければならない状況も考えられる。エンゲル係数(家計の消費支出に占める食料費の割合)が高い家庭ほど、その影響は深刻になるであろう。
店頭価格が高騰すれば、消費者は購入するコメの量を減らしたり、より安価な銘柄を選んだり、あるいはパンや麺類といった他の主食で代替する頻度を増やすといった行動をとる可能性がある。
特売品を求めて複数の店舗を回ったり、ふるさと納税の返礼品でお米を選ぶといった対策をする人も増えるであろう。また、外食産業でコメの仕入れ価格上昇分が定食や丼物などの価格に転嫁されれば、消費者が外食を控える動きにつながる可能性もある。
これまでは味や産地にこだわってコメを選んでいた消費者も、価格高騰が続けば、品質よりも価格を優先する傾向が強まるだろう。また、まとめ買いをして冷凍保存するなど、少しでもお得に購入しようとする動きや、節米レシピへの関心が高まることも予想される。
政府や関連機関には、備蓄米の計画的かつ効果的な放出といった短期的な価格安定策に加え、生産者への支援を通じて国内のコメ生産基盤を強化し、消費者が安心してコメを購入し続けられるような中長期的な取り組みが一層求められる。
また、価格が高騰した場合には、特に経済的に困難な状況にある家庭への支援策も検討されるべきである。
消費者としては、日頃から複数の銘柄の価格動向をチェックし、政府の備蓄米放出に関するニュースにも注意を払うなど、情報を得て賢く対応する姿勢が大切になる。
また、コメだけでなく、パンや麺類などもバランス良く取り入れたり、地産地消を意識し、地元産の野菜や他の穀物を積極的に消費するといった、より広い視点で食生活を考える機会を持つことも求められる。
AIの予測も参考にしながら、家計と相談し、無理のない範囲で日々の食卓を守っていく工夫が必要な時代といえる。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主席研究員 テクノロジーリサーチャー 柏村祐)