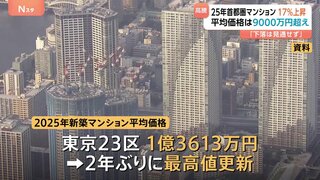在庫管理体制の再構築
米の生産はおおむね年1回の循環で行われており、長期備蓄を民間が担うことは費用面で現実的ではない。
このため、安定的な供給体制を確保するには、国による備蓄米制度の再構築が求められる。
現在、政府は「食糧法」に基づき毎年約20万トンの米を買い入れ、最大100万トンを上限として備蓄。
5年間保存した後、品質が劣化する前に飼料や加工用に転用している。備蓄米は、災害、異常気象、価格高騰、需給不安などの場合に、農林水産省の審議会意見を踏まえ、農林水産大臣が放出を判断する仕組みとなっている。
1|備蓄米放出制度の機動化
現行制度では、米価格が高騰した場合に備蓄米を放出するための具体的な審議会開催基準が設定されておらず、審議会での意見集約や大臣の判断を経て備蓄米放出の決定に至るまでに、一定の時間を要する構造である。
その結果、今回のような米価の急騰に際して、適切なタイミングで放出判断を行えなければ、価格高騰を助長する事態を再び招く恐れがある。
このため相対価格・市場価格・民間在庫量・作況指数などの客観的指標に基づき、あらかじめ基準値(トリガー)を設定し、それに達した場合に自動的に備蓄米の放出を判断できる制度の導入が求められる。
2|備蓄米の在庫・買戻しルールの見直し
備蓄量・備蓄期間を再検討し、必要時に備蓄を十分に活用できる体制とする。
また現在の「放出量と同量を翌年買戻す」制度は、需給ひっ迫が複数年続いても翌年に買い戻す仕組みとなっているため、その買戻しにより既にひっ迫した市場在庫を更に圧迫させるリスクがある。今後は買戻しルールの見直しも含め制度の柔軟化が求められる。