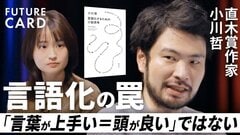なぜ「ひとり焼肉」と言うのに、「ひとりコンビニ」とは言わないのだろうか
現実的には、誰もが何かしら一人での消費行動を行っている。コンビニやスーパー、図書館、病院、市役所など、複数人で行く必要性がなかったり、一緒に行く誰かを見つけていくという労力やコストをかけてまでも行く必要のない場所に行く場合である。そこに行く時はわざわざ「ひとりコンビニ」「ひとり市役所」といわないのに焼肉やカラオケなどには「ひとり」という言葉が付与されるのは、消費するモノや場所によって、無意識に線引きしているからだ。テーマパークや焼き肉などを一人で消費するという事は、それが他人と「共有」されるべき体験という「普通の枠組み」から逸脱していると見なされてしまうからである。だからメディアではどこから「ひとり○○」が難しいですか?といった、そのボーダーラインをインタビューやアンケートをとることで、何を一人で消費するコトが異質なのかを視覚化し、異質である対象を特殊なモノとして扱う。ただ、そのような線引きは、その消費者が置かれている環境や嗜好するモノにおいて大きな差が出る。
「ひとり○○」で最もハードルが高いと言われるディズニーリゾート。参考値ではあるが、Z世代に特化したマーケティングを行う株式会社MERYの「MERYユーザーアンケート(2023年11月実施)」では、東京ディズニーリゾートへは誰と行くことが多いのか聞いているが、「1人」は1.3%と超少数派であったという。しかし、筆者のようなディズニーオタクの中には、むしろ一人で行くことの方がスタンダードと考える者も少なくないだろう。また、年間パスポートがあった時代、近隣住民はいわゆるオタクでなくともそれを所持し、散歩がてらにふらっとパークを散策していたという。その時そこは彼らにとっては社会一般にいう観光地としての家族旅行やデートとしての「場」=コンテクストではなく、「近所の公園のようなもの」という違う文脈で消費されていたのだ。「ひとりコンビニ」や「ひとり市役所」と何ら変わりはない。
また、たまたま出張で地方に赴き、商談後に帰宅までの空いた時間で観光地を訪れても、誰もそれを「ひとり旅行」と認識しないのではないだろうか。なぜなら出張は一人で行くことが普通だからだ。旅行は一人だと特別なモノとみなされるのに、出張のついでの観光は特異なモノとしてみなされない(みなさない)のは、その消費行動の内容や本質ではなく、ただ旅行か出張かという、形態やモチベーションのみで線引きされているだけなのである。
併せて筆者のようなオタクと呼ばれる消費者や、それを消費するコトを生業にしている人々(フードライターなど)からしたら、それをひとりで消費するコト自体が日常的であり、消費に対するハードルは低いだろう。環境、消費機会、消費頻度、消費対象の多様化など、消費する消費者そのものに多様性がある(=画一化していない)のだから、消費する人数そのものにわざわざ意味を見出す必要があるのかと思う。