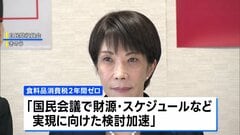米国のインフレ圧力が再燃してきた
こうしたトランプ関税を前に、米国の消費者物価(1月)が前年比3.0%という高い伸び率になった。これでFRBの利下げは当分の間先になったとみられている。FRBは、次回のFOMCで政策金利の見通しを公表する。次回のFOMCは、3月18・19日の日程だ。それまでに2月の消費者物価も発表される予定だ。
トランプ関税のインパクトは、当初に警戒されていたほどではないとしても、2月以降の物価指標には何らかの影響を与えていくだろう。だから、それを踏まえてもFRBが利下げに前向きになるとは考えにくい。
少し気になるのは、米国では各種のトランプ関税の導入を警戒して、輸入前倒しが1月以降に徐々に進んでいる点だ。こうした要因は、BtoCの消費者物価段階にはあまり織り込まれていないだろうが、BtoBのところにはより明確に影響が働いて、一時的にしろ物価の前月比を押し上げる要因だと考えられる。
物価指数では、前月比の変化も注目される。米消費者物価は、11月は+0.3%、12月は+0.4%、2025年1月は+0.5%とインフレ圧力が徐々に高まる格好で推移している。これからトランプ関税が実行されるという手前から、米国の限界的なインフレ圧力が高まっていることは、非常に見栄えが悪い展開だと思われる。
トランプ政権、インフレ抑制への一手とは
トランプ政策はどうしてもネガティブな側面に意識が行きやすい。敢えてプラス面を探すと、ウクライナ・ロシアの間の停戦交渉であろう。
仮に、短期間で停戦合意が成されれば、それはインフレ要因を減圧する。例えば、トランプ大統領がロシアに対して、原油輸出の拡大をアメとして持ち出すとそれは世界の原油市況を下落させることになる。化石燃料の消費拡大に躊躇する気持ちがないトランプ大統領だからこそ、そうした点を交渉材料に使ってくる可能性はある。
一方、ウクライナのゼレンスキー大統領には、停戦交渉で利得は相対的に少ない。領土の割譲を許せば、求心力は低下してその地位も危うくなる。ロシアの侵略リスクが根強く残ることも懸念材料である。合意に漕ぎ着けるのはかなり困難だとみられる。