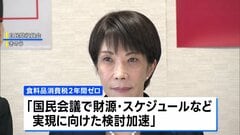インフレ懸念で全輸入品への関税シナリオは後退
攪乱要因であるトランプ関税について見ておこう。全体観としては、当初、警戒された全輸入品への10~20%の関税率の適用はほぼなくなったのではないだろうか。
もしも、これが実施されていれば、「(輸入財額×10%)÷名目GDP」で近似的に計算して、米国の物価が1%程度は上がっていくインパクトであっただろう。しかし、目先、そのシナリオが大きく後退している。その点は評価できる。
一方、その流れは一律関税から個別の関税適用に変化している。相手国・商品別にトランプ関税は細分化してかけられる格好になるだろう。すでに実施されたのは中国向けに10%の輸入関税の追加(2月4日)である。メキシコ・カナダは、3月初めまで協議を継続して、そこで実施するかどうかを決定する。
中国だけに限ってみると、2024年の全輸入額のうち中国輸入の占める割合は13.5%と小さい(米商務省統計)。それと対比すると、メキシコ・カナダの27.9%のシェアは大きい。仮に、この両国に25%の関税率がかけられれば、近似的に物価に対するインパクトは0.8%ポイントと大きくなる。
トランプ関税、日本へのインパクトは
日本については、石破・トランプ会談(2月7日)で全輸入品に関税率をかけるというアナウンスはなかった。
しかし、会談直後にトランプ大統領が、鉄鋼・アルミに25%の関税をかけると表明した(3月12日から実施の見通し)。こちらは日本も含まれていて、全輸入相手国が対象である。しかし、鉄鋼・アルミ(含む加工品)の輸入シェアを調べると、こちらは2.0%と小さく、そこへの関税適用がマクロのインフレにつながる可能性は相対的に小さい。
トランプ大統領は、ほかの項目についても、関税率の引き上げを言及している。半導体、医薬品、石油・天然ガス、銅といった品目だ。いずれにしても、輸入シェアはそれほど大きくはない。
また、今後の交渉によっては、除外対象国になる可能性があったり、関税割当(一部数量の適用除外)などの条件緩和がある可能性はある。オーストラリアは、対米貿易黒字がないので、鉄鋼・アルミのトランプ関税は除外される見通しだ。
さらに、トランプ大統領は相互関税を持ち出している。相手国が関税をかけているときに、同率の関税をかけて対抗するという措置である。その実施は、4月初旬から始まるとみられている。日本は農産物の分野で米国から相互関税をかけられる可能性がある。
大きく分けると、①メキシコ・カナダ交渉、②鉄鋼・アルミ関税、③相互関税、の3つの方面でトランプ関税が実施されていくことになろう。今後、各国は、2~4月にかけて米国と協議して、適用取り下げ等を議論することになる。
今後の交渉次第で関税適用の範囲などが変化することは、マーケット心理に対しては、「はらはらさせる」要因になって決してプラスではない。当面、マーケット心理をかき乱すトランプ関税という「妖怪」が、株価の下押し要因となり続けることが懸念される。