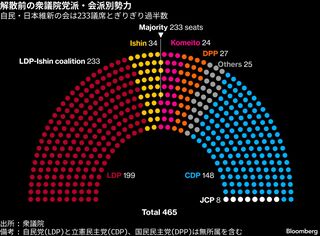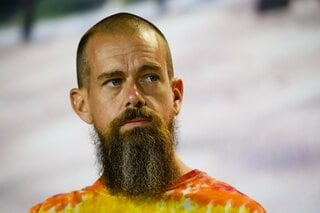インセンティブと損失回避の心理が決め手?~ソーシャルマーケティング視点で見る普及の鍵
それでは、これらの実態について、ソーシャルマーケティングの視点からはどのような考察ができるだろうか。たとえば、キャッシュレス決済ポイントという金銭的なインセンティブを提供したことで、消費者に具体的かつ即時の利益を提示し、カード取得に対する行動変容を引き出すことに成功したと考えることができるかもしれない。金銭的インセンティブはソーシャルマーケティングにおける重要なツールであるが、この提供により、人々が行動を起こさない理由(たとえば、手間や時間のかかる手続きなど)を克服し、自ら行動を変えた可能性がある。
また、第二弾事業においてポイント申し込み期限が幾度となく延期された影響についても興味深い。ソーシャルマーケティングや行動経済学において、行動に対するインセンティブに時間制限を設けることは、意図した行動を促進するための効果的なアプローチとして知られているが、申請期限の度重なる延長によって人々に生じた「今、行動しないと機会を失う」という緊迫感が取得行動を促したという見方もできるだろう。実際、2023年度の年間発行枚数1426万枚のうち、83.5%が申請期限の9月末までの期間に集中していたことからも、その駆け込み度合いが見て取れる。つまり、申請期限の設定とその延期が、ポイントを得る機会を逃すことが人々に損失として認識され、それを回避するために、具体的な行動を起こす動機付けに繋がった可能性がある。
この様にマイナンバーカードの普及が進み、政府のデジタル行政サービスは信任を得て、大きく前進する機を得た様に見える。しかしその一方で、デジタル庁は冒頭の重点計画の中で、「社会のデジタル化に対して良いと思わない」との声が一定数存在することを指摘している。そこで次回は、デジタル行政サービスに対する人々の意識の観点から、行政のデジタル化の「今」を考察してみたい。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 研究員 小口裕)