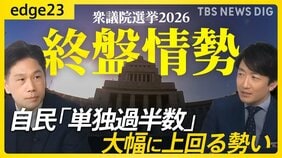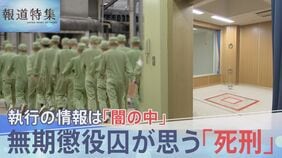しかし、今から180年以上前の江戸時代に栽培が始まったとされる伝統の綿内れんこんも、現在作っている農家はわずか数軒。
小学生を収穫体験に招いた堀重文さんの父で、この道50年以上という三喜男(みきお)さんも、現状に寂しさをにじませます。
堀三喜男さん:
「(昔は)仲間も30人くらいいたみたいだし。今はいないんだな」

堀重文さん:「自分が始めたときにはもう4,5軒くらいになっていて、今は2、3軒という感じ」
「やっぱり減ってきちゃうとね、みんなでおいしいといわれると、これを守っていかないといけないというのを、今は思っています」
伝統の「綿内れんこん」を守ろうと活動している人が、長野市松代町にいます。
青果店「野菜のカネマツ」の小山修也(こやま・のぶや)さん。
10年ほど前、堀さんが作る綿内れんこんと出会いました。
小山修也さん:
「レンコンだけの料理って、そもそも初めてだったんで、自分も食べてみたとき衝撃で、こんなおいしいんだと思って」
小山さんをとりこにしたのが、堀さんの家で出された「レンコンの酢煮(すに)」。
作り方を、小山さんの母・都代(くによ)さんに教えてもらいました。

用意するのはレンコンと水、薄口しょうゆと砂糖に酢、塩、油。
まずレンコンの皮をむき、薄くスライスします。
小山都代さん:
「粘りがあるのが特徴なので、粘りが出てきています」
スライスしたレンコンを水に浸したあと、弱火でゆっくり炒め、透き通ったらレンコンをつけていた水を投入します。
小山都代さん:
「水がまた粘りとうまみを出す。でんぷんが豊富だから」
「こういう風にとろーっとなってきて…」

そこに醤油などの調味料を加えてさらに炒めたら、「レンコンの酢煮」のできあがりです。
伊藤記者:
「粘りがあるからとてもまろやか、うまみがギュッと詰まっている」
小山都代さん:
「とろみを出すというのを堀さんに教えてもらって本当にすごいなと思って。綿内れんこんだからこそだと思うんですよね」