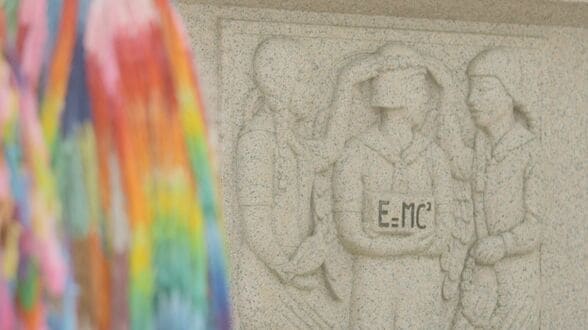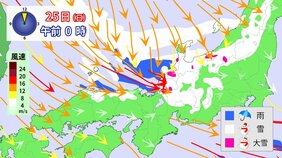広島市立大学 国際学部 武田悠 准教授
1975年ですので、その2年前に石油危機というのがありました。中東諸国、アラブ諸国、石油をいっぱい持っている国とイスラエルとの間で何度も戦争していたんですけれども、その中で産油国の側が石油を武器として使うわけですね。自分たちの持っている石油の値段を上げたりだとか、今後、たとえばイスラエルを支援する国には輸出をしないかもしれないという脅しをかけてくるということがあった。これで日本国内だけじゃなくて、世界的にパニックになって、物の値段がたいへんなインフレになったわけですね。どの国も経済に大きな影響があって、それぞれの国でそれぞれバラバラに対処していると困ると。みんなで協力してやらないといけない。どの国も石油がないと困るし、かといって、たとえば1つの国が高いお金を出して石油を買おうとしたら、ほかの国がそのぶん減ってしまうので、迷惑をこうむってしまう。経済的にも同じように自分の国を守ろうとして、ほかの国に迷惑をかけるということは今と同じで、だんだんと世界経済がつながり始めた時期ですので、主な先進国が集まって、どういうふうに対応しようか話そうということで始まったのが、サミットでした。
本名正憲 アナウンサー
なるほど。トップ会談みたいなもんですよね。最初のサミットはカナダが入っていないからG7(先進7か国)ではなくて、G6。この「G」とは、どういう意味?
武田悠 准教授
Group of seven。英語だともう少しニュートラルというか、単純な意味になるんですよね。7か国の集まりみたいな感じになります。
本名アナ
その7か国に日本も入れていただきまして、ありがとうありがとうございますと国民としては思うわけなんですけども、“すったもんだ” があったんですか?

武田悠 准教授
水面下ではいろんな駆け引きがあって、最初、これを考え出したのはフランスとドイツなんですね。この2か国がやろうと。アメリカは入っていなかったんです。最初はヨーロッパのほう。アメリカは経済力からいっても、軍事力からいっても当時の西側諸国、民主主義とか資本主義とか自由市場経済という国々のリーダーなわけです。基本的には自分でやることは決めたいわけです。でも、ほかの国はアメリカにいろいろ好き勝手されると困るということもあるので、アメリカもほかの国も巻き込んで、こういうサミットみたいな枠組みを作っておくと、アメリカの暴走に歯止めをかけられるという面もある。こういう会議っていうのは、だいたい、ヨーロッパが提唱することが多いですね。昔からこういう主要国を集めるという会議は、ヨーロッパが、経験が非常に豊富なのでいろんなノウハウがあるということもあると思います。どういうふうにしたら、みんな集まってくれるか。
本名アナ
なるほどね。フランスとドイツの話の中で始まった。第2次世界大戦の戦勝国と敗戦国の間でというのは、戦争が終わってから時間も経っていますけれども、おもしろいのは、日独伊と英米仏なんですね。
渕上沙紀 アナウンサー
ああ、そうか。ほかにも入りたいっていう国はないんですか?
武田悠 准教授
ありました。当時からずっとサミットに対してそういう批判があるんです。一部の国だけが集まっている。自分たちを入れていないと。特にヨーロッパからは4か国出ているんですよね。フランス・ドイツ・イギリス、あとからイタリアも入ったんですけど、最初はイギリスまでだったんです。3か国で、アメリカも入れて「4」でやろうとしていたんです。そうしたらアメリカが日本を入れないとダメだと。経済力がすごく大きいから無視できないと。ヨーロッパは戦勝国であるわけです。日本に対して70年代当時、すごく差別意識もあるし、一方で経済摩擦も始まっていて、あんまりいい感情はない。本当に入れるの?というのをアメリカが説得して、日本が入るんですね。そしたらイタリアがへそを曲げる。つまり、ドイツが入っているのに何でうちが入ってないのって言い始めて、ほかにもいろいろ事情があったんですけど、さすがにイタリアにへそを曲げられると困るということでイタリアを入れたんですけど、ほかのスペインやオランダがうちはどうなると言い始めて、さすがにそこは断って、ようやく6か国で始めて、そうしたらアメリカがヨーロッパが多すぎるって言って、カナダを無理やり引きずり込んで、ようやくG7になったという感じで、本当に紆余曲折があったんですね。
本名アナ
参加国をめぐっても、G20があったり、グローバルサウス(新興国・途上国)といわれる国もあったり、変わってきていると思うんですが、いまだにG7に入れてほしいという国はいるんでしょうか?
武田悠 准教授
どうなんでしょうね。今はどっちかっていうと、G7以外の枠組みでという考え方の方が多いんじゃないでしょうか。G20という別の枠組みもあります。グローバルサウスという途上国・新興国、新しく出てきたインドや中国など、そういう国を巻き込んで、そっちの方でむしろやろうとしている、G7はもう古いという考え方で、2000年代・2010年代はすごく力を得た時期がありました。
本名アナ
開催地ですが、参加国以外の第三国でやったケースも珍しいもありますね。ベルギー・ブリュッセルサミットというのがありますが?
武田悠 准教授
これは、非常にイレギュラーだったんです。2014年です。このときはロシアが当時はまだ入っていて、「G8」だったんです。ところが、今、戦争をしているウクライナのクリミア半島をロシアが無理やり併合したということがあって、それまでにもすでにロシアとほかの西側諸国、アメリカ・ヨーロッパ・日本はいろんな対立があったんですけども、これでいよいよ、もうこの枠組みには入れておけないということでロシアをこのとき、外に出したというか。この年、ちょうどロシアでやる予定だったんです。で、やめようと。それをやってしまうと、ロシアのクリミア併合をあたかもG7が承認したかのように思われてしまうということがありますので、急きょ、ブリュッセルでやった。ブリュッセルは、いろんな国際機関の本部が置かれていて、特にNATO(北大西洋条約機構)というアメリカとヨーロッパとカナダの同盟条約みたいなものですね。多国間の条約があって、そこで開くことは、つまりロシアのクリミア侵攻に対する対応を話し合うんだというような意味合いもあって、ここで開催したということになるわけなんです。