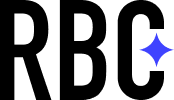我が子の口に布をあて窒息させる人の姿を見て、真喜屋さんの母は決断しました。
▼真喜屋光子さん(80)
「とにかく赤ちゃんを守ること、とにかく私を守ることだけ、死ぬときはもう一緒に…。ここで赤ちゃんを渡して生き残ろうという気持ちはなかったから、壕から祖母も一緒に出てきたと話していた。そこからはもう木の下に隠れたり…」
壕を出て、再び戦場をさまようことになった一家。沖縄本島中部の洞窟に身を潜めていた時に、米軍の捕虜となりました。
「最後まで生きてはいたけど、生きては帰れない」

一方父は、娘の顔を見ることなく戦死。そして、終戦から2年ほどたったある日、父の部下だったという男性が訪ねてきました。
県の農林課にいた父は、沖縄戦当時、牛島満中将ら幹部の食料隊長として従軍していました。摩文仁で牛島中将が自決したあと、食料係として動員されていた民間人およそ20人に、こう告げたといいます。

「『自分は死ななきゃいけないけど、みんなは生きて、次の世は必ずあるから生きていなさい』と言って、(自決用の)青酸カリをみんなから取り上げたと―。『名護の方に避難した妻が生きていれば、ちょうど子どもが生まれているかもしれない。自分は最後まで生きてはいたが、生きては帰れないということを伝えてくれ』と―。父が部下たちに『次の時代に生きろ』と言ったこの英断は、娘として誇りに思います」
戦時下に産声をあげた真喜屋さん。80歳となった今も、父を思い、その足跡をたどり続けています。

「あの当時、大変な時代に、沖縄のためにという(思いを持っていた)人たちがたくさんいらした。そういう方たちが自ら命を絶ったということが、私はすごく悔しいと思うんですね。そういう素晴らしい方たちが亡くなる。自ら命を絶たせた責任はどこにあるんだろうと、いつも思いますね」