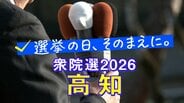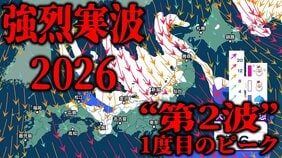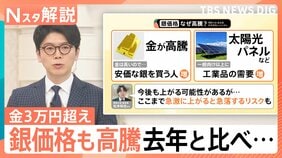500キロ離れた高知から何度も能登半島に通い、給水活動を続けている男性がいる。災害用浄水装置を開発・製造している、武田良輔さん(44)だ。社長兼職人。社員ゼロ。人生をかけて“命を守る水”を生み出し続ける。
1か月の半分は能登半島地震の被災地で給水活動
2024年1月1日、新たな年が始まったばかりの石川県・能登半島を襲った大地震は各地に甚大な被害をもたらした。
高知市で浄水装置を開発・製造しているアクアデザインシステムの社長、武田良輔さんは、発災直後の1月3日、給水支援のため能登の被災地に向かった。これまで、西日本豪雨や熊本地震などの被災地でも給水活動の経験のある武田さんだったが、能登半島の被害状況は「これまでで一番深刻だった」と語る。
長引く避難所生活に加え、断水がいまだ解消されない地域もあり、武田さんは4月までに、高知と石川県を8往復。学校など15か所に、自社の浄水装置を高知から運び入れ、飲み水を始め、シャワーや循環式の風呂の提供など、被災者に寄り添う活動を続けている。
最初に訪れた珠洲市の学校では、近くの砂防ダムにたまった水を浄水し、飲み水や生活水として供給。まだ雪も降るような真冬の能登で、日中寒さに耐えながら、夜は、車で寝泊まりしながらの給水活動だった。

▼武田良輔さん
「自宅に電気が回復し始めると避難所から自宅に戻る人が多くなる。でも断水が続いているから、車で遠くから水を取りにくる人もいました。みなさん、不便な生活を強いられているのに表情に余り出さないんですよね。私にも暖房器具を持ってきてくれたり、『ありがとう』と何度も声をかけてくれたり、それがすごく励みになりました」
人々の命をつなぐ水。武田さんが浄水装置の開発を始めたきっかけは、泥水を飲むアフリカの子どもたちを目にしたことだった。