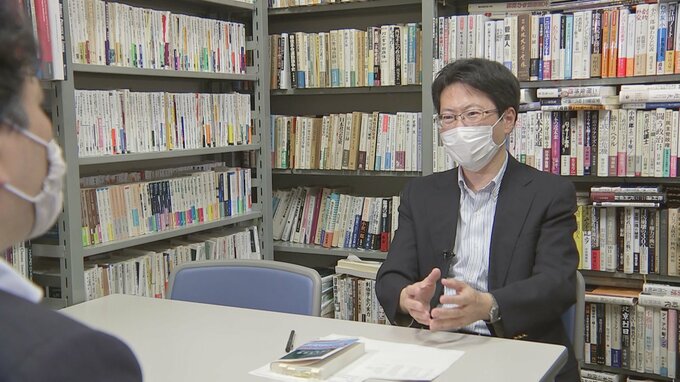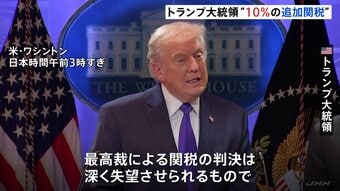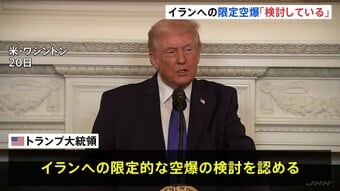ーー志位委員長は「一致点を持って協力する」と繰り返しています。
何かに反対するだけであれば、一致点だけでいいと思います。ただ、政権を日々動かしていこうということになると、ある程度の共有している方向性がないとなかなか難しいのではないでしょうか。
突発的な安全保障上の事態は起きます。今回のウクライナの問題で、ウクライナにどんな支援をするのか。武器まではいかないけれど防弾チョッキはどうかと、共産党の中でも一時期、田村政策委員長は「反対しない」と言いましたけれども、やっぱり駄目ということになった。さらに例えば大企業、財界について法人税の問題など、常にこういったところも問われてくる。もちろん共産党も一定程度妥協するかもしれませんけれども、日米同盟強化は絶対駄目とか、自衛隊も現状維持まではいいけど、強化は駄目という態度では、なかなか外交・安全保障上の変化に対応できない可能性が出てくるのではないか、ということをやはり立憲民主党は心配しているのだと思います。

ーー共産党は今後、どのように変わるべきでしょうか?
先進国で共産党のまま、非常に党勢が伸びている政党はありません。中国など、その国の体制、制度になっているところは別ですけれども、ヨーロッパなど先進国の共産党は大筋において低迷しているか、あるいは大きく転換したか、どちらかです。
一つの可能性はイタリア共産党です。イタリア共産党は西側で、冷戦期最大の共産党でしたが、ソ連が崩壊する時期に大きく転換して、いわゆる社会民主主義政党に変わっていき、その過程で政権を担う、そういった政党になっています。資本主義や議会制民主主義の枠内で、改革、改良に努めるというのが一つの選択肢です。おそらくそこまで転換してくると、立憲民主党との距離がぐっと縮まって、日本でも野党連合政権という形になれば、共産党も十分に担えるところに入ってくるのではないかと思います。
もう一つ選択肢があり、いわゆる民主的社会主義と言われるものです。方針としてはかなり急進的な左派で、代表的なのはドイツの「左翼党」やフランスの「不服従のフランス」などです。こういった勢力はジェンダーやフェミニズムなど、より多様な目標を掲げて党内も多様性を認めていく。どちらかというとボトムアップの運営をしていくということです。そうした政党がヨーロッパでは共産主義政党に変わって、急進左派の主力になってきています。こういった政党に変わってくれば、若い人たちを巻き込んで大きなうねりを作っていくということも可能になるのではないでしょうか?
日本社会でもこれだけ格差が広がっていて、他の国を見れば、若い人の中で左派的な流れが強まっていると共産党は、しばしば言及します。しかしなぜ日本でそういう流れが強くならないのか。私は受け皿が弱い、共感を得る形になってないということじゃないかと思います。
その受け皿に共産党になるということが、現実の課題として平和や平等、人権というものを推し進めることに繋がる。何年先のことかわからない共産主義に基づく革命、社会主義、共産主義社会よりも、当面の平等や平和の実現に力をつくそうとするならば、共産党がこれまでの考えを含めて、見直していくと。それが、ある意味で共産党の本来的な理念を生かすということにもなるのではないでしょうか。
根本的には共産党は、平和や平等という価値を追求するということだと思います。ただ追求の仕方は、従来の共産党のまま追求するしかないのか。いろんな形態がありうるわけで、そういったことを含めて転換を考えるべき状況に入ってきているのではないかと思います。