また、元日の地震では課題も見えました。車で避難する際の「避難経路の確保」です。

柏崎市の避難計画では原発事故が起きた際、北陸道と国道8号が糸魚川方面へと向かう住民の避難経路となりますが、今回の地震では上越市の国道8号で土砂崩れが起きたほか、路面のひび割れや段差などの影響で北陸道も通行止めとなり、14時間余りにわたって、同時に通行が不可能になりました。
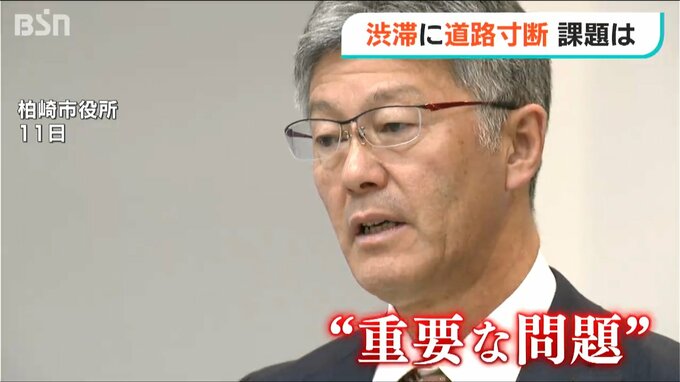
これについて柏崎市の桜井雅浩市長も、「重要な問題だ」と受け止めています。
「糸魚川市に行く動線は2つしかない。国道8号と北陸自動車道。(原発事故時は)市民の約75%の方々が上越・糸魚川・妙高市のほうに避難する。糸魚川に至るまでの動線がひとつ今の段階で(実際に一時)閉鎖されている」
宮川集落で町内会長を務める吉田さんは、2007年に起きた中越沖地震を振り返り、「閉じ込められるというか、孤立する感じはあった」と話します。

中越沖地震では、柏崎市や刈羽村などは最大震度6強の揺れを観測しました。
自宅近くの道路は寸断され、土砂崩れも発生。実際に一時孤立した地区があったことから、その後は陸路ではなく海路=船での避難訓練も行われてきましたが、今回の地震では海から離れなければならない、「津波警報」が発表されました。
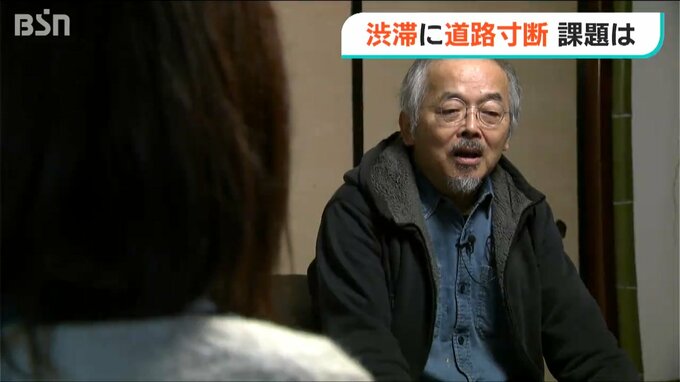
宮川町内会 吉田隆介会長
「やっぱり逃げる方法は本当に限られていて、ヘリコプター以外ないと思っている。ただ、ヘリコプターだと乗る人数に制限がある。それを回転させることがどこまでできるか。形だけの『大丈夫ですよ』と、『こういうふうにして逃げられますよ』と言っているけど、現実にそれがどこまでやれるかというのを私たちは非常に疑問に思っている」














