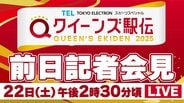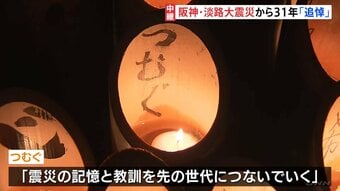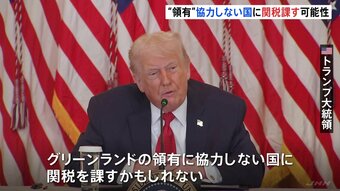東日本を意図的に抑えたことの効果は?
大迫プレイングダイレクターのプッシュもあり、11月3日の東日本実業団駅伝は“ペース走”として走った(17位)。10月15日のMGC(マラソン・グランドチャンピオンシップ。パリ五輪代表3枠のうち2人が決定)から僅かの日数しかないため、MGC出場選手が在籍するチームは、地区予選を完走さえすればニューイヤー駅伝に出場できた。そのシステムをGMOは活用した。
「100%の週間マイレージを積んで行くことができました」と亀鷹監督。「通常は東日本の前に一度、(大会にピークを作るために)練習を落とします。それをなくして、距離や強度は選手によって違いますが、各選手が100%の練習をし、東日本で出し切っていないことでタメを作ることができました」
しかし練習でタメを作るのは、目に見えにくい部分、選手は実感しづらい部分である。
もちろん、そのあたりはぬかりない。スタミナ的なところは「毎週日曜日は必ず、30km走などロングランを入れてきました」と亀鷹監督。年明け2月、3月のマラソンを目指す選手が、ニューイヤー駅伝まで1カ月を切っても40km走を行う例はある。だがGMOチーム全体でいえば、そこまでマラソンを予定している選手は多くない。
「ペース走をやっても離れる選手はいません。そういったところでも、タメを作ったことで選手が粘れるようになっています。ですから、駅伝でブレーキ(区間順位、タイムが想定を大きく下回ること)することは考えられません。確実に走れるベースができました」
スピードのチェックは11月25日の八王子ロングディスタンス10000mで行った。
「八王子も80%の力で行きました。28分20秒を切るくらいの走りをしよう、と。ただ、岸本だけは(長距離選手の肩書きの1つである)27分台が出せそうな状態でした。27分台を出すことで自信になるということで、少しスピードを出しました。八王子もチームとして、ほぼ予定通りの走りができました」
現場の選手とスタッフが、初優勝を狙えるチーム力をしっかりと作り上げていた。
大迫は何区に登場するのか?
八王子ロングディスタンス10000mでは岸本が27分54秒91の自己新で走り、村山28分18秒88、大迫28分19秒31、吉田28分19秒48と3選手が予定通りのタイムで走った。嶋津は4人と比べるとトラックのスピードで劣るが、28分27秒32と合格点の走り。
今江は同じ週の日体大長距離競技会5000mに出場し、13分33秒32の自己新だった。東日本実業団駅伝が練習のペース走代わりとして有効だったことが、この結果で実証された。その後ケガ人や体調不良者が出たり、急激に調子を上げてきた選手が現れなければ、両大会の結果から以下のような区間配置が予想できる。
1区:村山紘太
2区:今江勇人
3区:岸本大紀
4区:クロップ
5区:吉田祐也
6区:嶋津雄大
7区:大迫傑
亀鷹監督は会見で区間配置については以下のように言及した。
「前回1区は最高のスタートを切りました。今回も先頭で来ると思いますが、最長区間になった2区と3区では、トヨタ自動車と旭化成の方が少し力が上かもしれません。そこは30秒以内でしっかりつける。(インターナショナル区間の)4区のクロップが他チームの外国人選手より1枚も2枚も上なので、そこでトップに出る。4区が終わってHondaに20~30秒は勝っておきたい。あとは向かい風となる5、6、7区です。確実に走る選手、駅伝に強い選手を揃えました。なんとか逃げ切りたいですね」
コメントから推測すると1区は前回に続いて村山が有力だ。ラストスパートで後続に数秒の差をつけられる選手。その数秒が2区の選手を走りやすくする。主要区間である2、3、5区は岸本、今江、大迫、吉田の4人から起用されそうだが、正直なところ予想はかなり難しい。
ハーフマラソンの実績やスタミナ型であることから、今江が2区最有力候補であるのは間違いない。だが今江だけ11月の記録会が5000mだった。長い距離に心配はないからスピードを強化している、と見るべきだが、スピードが予想以上だと確認できたことで、3区起用の可能性も出てきた。
10月のMGC(4位)を走った大迫のスピードが、前回と同じくらいに戻っていれば3区が有力だ。だが大迫が3区なら監督が「2区と3区ではトヨタ自動車と旭化成の方が少し上」と言わないのではないか。
亀鷹監督は岸本のことを「追い風でも向かい風でも、上りも下りもどこでも使える選手」という評価の仕方をしていた。スピードを生かすなら岸本3区の可能性はある。上りや向かい風の強さを生かすなら5区、または6区ということもある。
亀鷹監督は大迫の起用区間を質問され「わくわくする区間を走ります」と答えた。そうするとビハインドを覚悟している2、3区ではない、という推測が成り立つ。4区までにリードできなかったときに、5区か6区で逆転してトップに立つ、あるいは初優勝のフィニッシュテープを切る。そういった役割を大迫に期待しているのかもしれない。GMOの戦力が充実した今、大迫の復路起用も、選択肢に入ってきた。
個人的には、東京五輪のフィニッシュシーンが思い浮かぶ。6位ではあったが、アフリカ勢が席巻する現在のマラソン界では大健闘だった。本人もやり切った思いが強かったのだろう。周囲に手を振りながら、感無量の表情でフィニッシュした。種目も違えば立場も違う。大迫が同じ気持ちでフィニッシュすることはない。常識的にも、駅伝はアンカー勝負をあまり想定しない。
だが戦力的にマイナスとならないと判断されたとき、チームを象徴する選手に、チームの功労者にテープを切らせた例はある。群馬県庁に向かって走る大迫をイメージすると、わくわくするファン、関係者も多いはずだ。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)