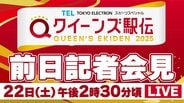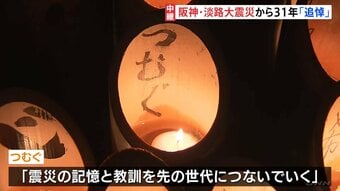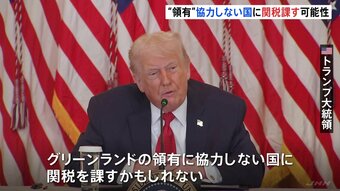兄弟が一緒に練習することの効果も期待大
4区の走りを悠太自身は「自分らしさを出せたレースでした」と感じている。最初から周囲の力を借りて走ろうという素振りは見せず、ものすごいハイペースで飛ばした。その走り方でエース区間の区間賞を取り続けた。マラソンでも19年MGCで37kmまで独走したり、東京マラソンで世界トップ選手の集団で思い切ったレースを展開してきた。しかし駅伝でどんなに前半から飛ばしても、後半で大きく失速したことはなかった。
「日頃からそういう失敗をする自分を想像していないからです。常に成功するイメージしか考えていませんから。そこじゃないですかね」
後半でペースダウンしないことを常に意図して練習をする。おそらく前半を速いペースで入る走りを、練習段階から繰り返していた。
冒頭の啓太のコメントにもあるように、兄弟は同じチームになったことを最大限に活用しようとしている。西鉄は普段のポイント練習を、選手全員が個々に考えるという。だが兄弟はジョグだけでなく、週に2~3日行う負荷の高いポイント練習を一緒に行うことも多い。
2人は大学卒業後10年近く、別のチームのメニューで練習してきた。すでに30歳を超え、疲労の回復なども個人差が大きく生じている。そんな選手同士が同じメニューを行うには、どんな話し合いをしているのか。
「いつポイント練習を行うかを、まず聞きます」と啓太。「距離は合わせたりしますけど、本数はその日の練習の目的を考えた結果違ったりします。タイムも、速く走りたい方が後からスタートして追いかけたり。1人でやるより2人でやった方が、質も高くなりますね」
2人のメニューや、設定タイムなど走り方をすり合わせる。それがスムーズにできるのは、双子兄弟ならではかもしれない。9年半違うチームにいても、大学まで育った環境は同じだった。お互いを理解し、リスペクトし合っていることが、30歳を過ぎた2選手の共同練習を可能にした。
ニューイヤー駅伝でのタスキリレーは実現するかわからないが、2人が同じチームになったことで、設楽兄弟がまた長距離界を盛り上げていく態勢が整った。ニューイヤー駅伝は二人三脚の最初の一歩になる。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)
※写真は左は悠太選手、右が啓太選手