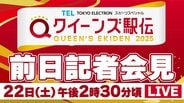大八木総監督のノビシロを残す指導法とは?
駒澤大出身選手が実業団に進んでから、特にマラソンで成長している。その理由を大八木総監督は「学生時代はノビシロを残す指導をしているから」と説明する。
だが現実には、目の前の駅伝に勝つことが求められる。駅伝に向けて全力のトレーニングをしなければいけないのではないか。そういう見方に大八木総監督は、はっきりノーと答える。「具体的には話せないところもあるのですが、量をさじ加減しています。(代表的なスピード系メニューの)インターバル走の量であったり、距離走の量であったり。実業団に行ってからこのくらい伸びてくれたらいいな、というところから逆算して、1年目でこのくらい走れたらいい、2年目ではこのくらい、3年目では、4年目ではとイメージできます。1年1年、力が付いていく中で、量的にいっぱいにならないところでやっています」。
しかし箱根駅伝で勝てない時期も続いていた。そこを乗りこえるためには、多少の無理はしないといけなかったのではないか。「4連覇した頃はすごく走りこんでいましたね、今は量をセーブしていますが。最近は(箱根駅伝であれば)勝てるメンバーが揃ったときに勝てばいい、という考え方です。実業団に行ってマラソンで成長したり、10000mで27分台を出したりするなど、ノビシロを取っておく。箱根もこのくらいのメンバーなら、このくらいの量をやれば勝てる、というノウハウがわかっていますから、実際この3年間で2回勝ちました。ですから普段は、学生の将来のことを考えて指導しています。箱根は勝てなくても(全8区間中9~13kmの距離が6区間の)全日本では勝っています」。
練習メニューの量的な部分のさじ加減が重要だと強調したが、それに加えて選手をその気にさせることに大八木総監督が長(た)けていることも大きいのではないか。いくらメニューを工夫しても選手が、「これ以上は無理」と考えたらノビシロはなくなる。
例えば目の前のレースに対しても、「このくらいの練習ができたら、このくらいの結果が出る」と予測を伝える。それが現実になり、何度も繰り返されれば選手は、指導者を信頼するようになる。その指導者が「学生でこのくらいやっておけば卒業後も伸びるぞ。代表になれるぞ」と言えば、選手はその気になる。
そうしたコミュニケーションを可能にするためには選手をしっかり観察し、その時点の選手の体調、心理状態を理解することが必要だ。しかし年齢が選手と離れると、その部分が難しくなってくる。選手気質が時代とともに変わると、コミュニケーションの仕方も変えないといけないからだ。それでも駅伝で結果を出すノウハウが確立されているから、ある程度の結果は出せる。そうなるとなかなか変更に踏み切れないが、大八木総監督は自身を変革し、以前のスタイルを変えることも厭(いと)わず選手とのコミュニケーションをしっかり行ってきた。それが指導者になった当初からの目標である、世界で戦う選手を育てるために必要
だったからだ。
しかし選手の気質は変わっても、目標とするのは競技で結果を出すことに変わりはない。個人でも世界で活躍することは、以前と変わらない夢である。むしろ、そう考える学生は増えている。
「駅伝の先に子どもたちの夢がある。それをかなえてあげたい」
大八木総監督の愛情があるから、駒澤大の選手は卒業後も頑張ることができる。
“駒澤から世界へ”。前回の中村に続き、今回のMGCでもその目標を駒澤大出身選手が実現する。
■MGCとは?
マラソンの五輪代表は16年リオ五輪までは複数の選考会で3人の代表を選んできたが、条件の異なるレースの成績を比べるため異論が出ることも多かった。そこで東京五輪から、男女とも上位2選手は自動的に代表に決まるMGCが創設された。MGCに出場するためには所定の成績を出す必要があり、一発屋的な選手では代表になれない。選手強化にもつながる選考システムだ。
五輪代表3枠目はMGCファイナルチャレンジ(男子は12月の福岡国際、来年2月の大阪、3月の東京の3レース)で設定記録の2時間05分50秒以内のタイムを出した記録最上位選手が選ばれる。設定記録を破る選手が現れない場合は、MGCの3位選手が代表入りする。大半の選手は絶対に代表を決めるつもりでMGCを走るため、一発勝負の緊迫感に満ちたレース展開が期待できる。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)