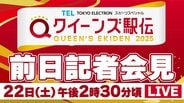スピード型選手とスタミナ型選手で異なる練習
“駒澤から世界へ”。大八木総監督はコーチに就任した当時から、教え子を世界で戦う選手に育てることを目標としてきた。1期生の藤田敦史(現駒澤大監督)が4年時には、出雲と全日本の両駅伝に優勝し、箱根駅伝(99年)で駒澤大初優勝の可能性があった。しかし大八木総監督は「今の藤田は、マラソンで結果を出すことを一番に考えていますよ」と話していた。
当時から大八木弘明総監督は選手のタイプを見て、強くなるアプローチ法をスピード練習中心の選手と、スタミナ練習中心の選手に分けて育成してきた。次第にそのやり方は洗練されていった。スタミナ型の選手とスピード型の選手では「スピード練習とスタミナ練習の組み方、構成の割合が違う」が、それがどんどん細分化されていき、より選手の個性に合うようになっている。
近年では山下と大塚に加え、二岡はスタミナ型の選手として育成された。それに対して西山と其田、小山はスピード型。中西は日本学生ハーフマラソン11位とロードでも活躍したが、トラックの5000m、1500mでの活躍が多いスピード型選手だった。
スタミナ型の選手は全員ではないが、練習状況を見ながら可能な選手は在学中に初マラソンに挑戦する。00年に日本記録を出した藤田らが確立したパターンだ。
「そこまでスピードがない大塚や山下には、マラソンをやったらどうか、と言っていました。そういう選手には(全区間20km強の距離の)箱根駅伝をやりながら、マラソンのためのトレーニングを経験させます。30kmのレースに出たり、練習で30km走を中心にやったり。30kmの距離をやれば箱根でも通用しますし、実業団に行った後のマラソン練習にもスムーズに入って行けます」。
大八木総監督が指揮を執り始めた90年代後半から箱根駅伝4連覇(02~05年)の頃までは、チーム全体でもスタミナ系の練習が多かった。その中でもトラックで活躍するスピード型の選手も育ったが、宇賀地強、深津卓也、高林祐介、高校時代に5000mで13分台を出した3人が入学した06年からは、スピード練習の設定タイムがどんどん上がって行った。
「スピード型の選手でも行く行くはマラソンをやったらどうか、ということはよく言いましたね。スピードがあれば中間走のときの余力が大きくなって、楽に走ることができます、スタミナがないと後半で一気にキツくなって減速してしまいますが、中間走ができる距離を伸ばしていくことやラストスパートに、スピードはつながります。西山は10000mの27分台、匠吾は5000mの13分30秒台を実業団で出してマラソンに進出した。其田も13分台を持って入学してきたスピード型ですが、在学中はそこまでトラックの記録が伸びませんでした。本人は大学を出たらすぐにマラソンをやりたい、という意思が強かったので、実業団2年目からマラソンに出始めることができたのです」。
大八木総監督には「マラソンでも世界と戦うときに重要になるのはスピード」という認識があった。スタミナ型の選手でも駅伝などを活用し、大塚と山下は10000mなら28分30秒台のスピードを学生時代に養成していた。