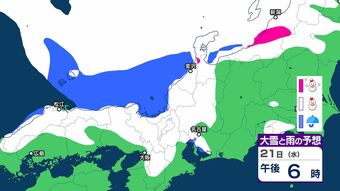■破壊された学校
ボロディアンカの街中に、一つの学校がありました。その学校の校長をしているという女性に、学校の中を案内してもらいました。ちょうど校長室の真上に爆発物が落下し、穴が空いている状態でした。ロシア兵はその学校もベースとして利用し、教室などで火を起こし、食べ物を煮炊きしていたといいます。

■ボランティアの若者
イゴールさんは、医療物資支援などのボランティアを続けています。攻撃が始まって避難している最中には、わずか100メートル先に爆弾が落ち、多くの人が亡くなったのを目撃しました。その後、戦闘が続いている状態の中でも、医療を必要としている人がいることを知り、医薬品を届ける活動をしていました。

彼は取材をしている私たちに、忠告もしてくれました。支援活動中のボランティア仲間が二人、地雷などによって大怪我をしたそうです。街中には、地雷、不発弾、そしてピアノ線を使ったブービートラップが残っています。支援も取材も、そうした危険性と隣り合わせであるため、注意が必要だというのです。
激戦区で聞く話は、どれも耳をふさぎたくなるようなものです。他にも、窃盗、拷問、性暴力など、さまざまな証言を聞きました。
■復興支援
イルピンで食事支援をしていたNGO「ワールド・セントラル・キッチン」(WCK)のスタッフにも話を聞きました。スタッフの中には、東部地域やヘルソン出身の方もいました。WCKはまず、キッチンを確保し、食材の流通を確保し、そして調理ボランティアを確保します。その上で、周辺地域の飲食店などの支援も受けながら、無料で食事支援を行います。このキッチンホールだけでも、1日に数千人に無料で食事提供を行なっていました。
私は今回の取材で、複数の場所で「炊き出しの食事」をいただきました。もちろんこちらは、「我々は取材に来ているので、避難者の方の食べ物をもらうわけにはいかない」と断ります。すると怪訝そうな顔をして、「何が問題なんだ?」「味を伝えるのも仕事じゃないの?」「お腹が空いている人に食事を出すのが私たちの仕事なんだよ」と言いながら、お皿にシチューを盛り、スッとこちらに差し出すのです。

ならばということで、提供されている食事を頂いたのですが、その味の美味しいこと。取材した日は5月のキーウ近郊にしては珍しく、10度以下の寒さで雨と風が吹き付けていました。寒さで凍え、なおかつ空いている店舗が限られている中、胃袋の中に、塩胡椒や出汁の効いたスープが染み込んでいきます。食べ終える頃には、体が温まりました。こうした食事支援で体を温めながら、他の場所へとさらに避難する元気を蓄えたり、片付け作業などを続ける方もいるのだなと、実感することができました。