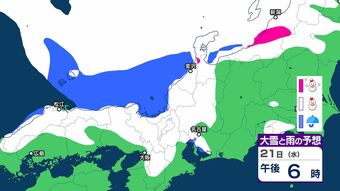■避難の実態は
ポーランドの首都、ワルシャワで、複数の難民の方に話を聞きました。そのうち、お一方のエピソードを紹介します。

17歳のアルテムさんは、3歳の弟であるプラトンくん、母親のオラさんと共に避難してきました。2月24日に戦争が始まってから10日ほど経った、3月3日のことでした。
母親のオラさんが避難を決断した最大の理由は、家族の安全のためでした。キーウ近郊で空爆が続き、シェルターに避難しなくてはいけない日々が続いたため、安全な生活が必要だと考えたのです。
移動も困難を極めました。鮨詰め状態の電車に10時間以上も立ったまま乗り、西を目指しました。空襲警報が鳴るたびに電車は止まらざるを得ず、なかなか目的地に着きません。夜になると、空襲を避けるために、電車の中は真っ暗になります。3歳のプラトン君を連れて行くのはさぞ大変だっただろうと聞くと、アルテムさんは「弟には、これはアドベンチャーなのだ、と説明し続けた」と言っていました。
アルテムさんの父親は、ロシアのモスクワで車の整備工をしています。父親もまたウクライナ人です。しかし、モスクワでのテレビ報道などに触れ続けているので、ウクライナなどの報道は「フェイクだ」と否定されます。家族が避難しなくてはいけない状態になっていると伝えても、話が通じません。なぜ家族の話より、ロシアメディアの話を信じられるのかはわからないと、アルテムさんはため息をつきます。
最近はウクライナに帰国する方も増えています。それは、一部地域などへの攻撃が落ち着いたと見られることもありますが、それだけではありません。家族などが心配で戻る方、義務感や罪悪感から戻る方もいますが、支援ニーズとマッチしなかったために戻る方もいます。
アルテムさんたちのホストファミリーとなっていた、ワルシャワ在住の寺田頼子さんにもお話を伺いました。例えば戦争勃発当初、隣国の多くの方が「支援するぞ!」と意気込み、ホストファミリーとしてホームステイをおこなった人もたくさんいます。その温かい支援で生活を維持できている方も多いのですが、他方で何週間か経つと、「やっぱり出て行ってくれないか」と追い出されてしまう方も残念ながらいました。

公的な支援も、私的な支援も、長期化すれば新たな課題が出てきます。難民受け入れをおこなった国だけでなく、国際的な財政支援や第三国定住支援など、長期的な「支援者支援」が必要だと分かります。