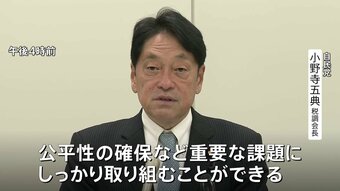良い生活習慣を妨げるものは?本末転倒な子育ての盲点

ーーつまり、最近の子どもたちは、早寝、早起き、朝ごはんなどの生活習慣が後回しにされているということなんですね。なぜでしょうか?
「まずは親の生活習慣の乱れによる影響があります。
さらに、乳幼児期から早期教育や、スポーツ教室に通わせる方が増えています。そのために、からだの脳を育てるべき時期に寝ることが疎かになっていることもあるようです」
ーー習い事は、小さいころから子どもにいろいろな経験させてあげたいと思ってのことだと思うんですが…。
「睡眠時間を削らないのであれば習い事も問題ないですが、寝ることを犠牲にするなら、本末転倒だから、やめたほうがいいです。特に乳幼児期は、夜8時に寝ることを死守してほしいです」
ーー夜8時を死守…そこまで大切だということなんですね。確かに、それを本当にできている家はそんなに多くないように思います。
「早寝ができないと、早起きができず、朝ごはんもしっかり食べられないわけです。
例えば5歳児だと、少なくとも10時間は寝てほしいんですね。10時間っていうと夜8時に寝て朝6時に起きる早寝早起きのイメージです。睡眠時間を確保できないと、脳の土台が作られなくなってしまうので、いくらその上に学習とかスポーツを入れても育たないわけです」

【望ましい睡眠時間】
●0-3か月 14-17時間
●4-11か月 12-15時間
●1-2歳 11-14時間
●3-5歳 10-13時間
●6-13歳 9-11時間
●14-17歳 8-10時間
●18-25歳 7-9時間
(出典:子育て科学アクシス)
ーー小学生でも9時間から11時間の睡眠時間ですか…。高学年になると塾に行く子もいますよね。「おりこうさんの脳」を育てることを優先するのではいけないんでしょうか?
「年齢が上がっても、やっぱり早寝早起き、十分な睡眠時間は大切です。しかも、規則正しい生活習慣は健康面だけでなく、学習面にも影響するという調査(※2)もあります」
ーーとにかく、良い生活習慣、早寝、早起きして、朝ごはんをしっかり食べることがなにより重要だということを、親は再認識しないといけないのですね。
「脳の育て方の順番をきちんとしていきましょう。繰り返しになりますが、生活習慣が軽視されると『からだの脳』が育ちません。『からだの脳』『おりこうさんの脳』『こころの脳』のバランスが崩れるということは、私達が思ってる以上に、子どもに大きな影響を与えるということを是非知ってもらいたいです」
(4月13日放送・配信『SHARE』より)
※1 文部科学省『通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査』 令和4年12月13日
※2 早稲田大学 理工学術院 柴田重信研究室とベネッセ教育総合研究所による『子どもの生活リズムと健康・学習習慣に関する調査2021』では、精神的な健康状態・成績が良い子どもは、普段から規則正しい生活をしている傾向がみられた。