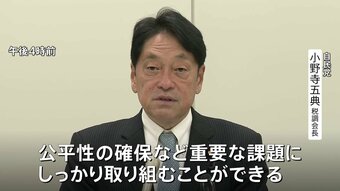発達障害の可能性がある子どもが、近年増加傾向だという。しかし、臨床経験35年の小児脳科学者は、その中には発達障害と「間違われている」子どもたちがいると指摘する。背景には、子育ての意外な盲点があった。
増加する子どもの不調 背景に生活習慣の乱れという盲点
文科省の調査(※1)によると、公立小中学校の通常学級で発達障害の可能性があり、特別な教育支援を必要とする児童生徒の割合が8.8%に上るという。単純には比較できないものの、前回の調査から2.3ポイント増だ。35人学級だとすると、1クラスに3人いる計算になる。
しかし、この子どもたちのすべてが発達障害とは思えないと話す専門家がいる。発達障害や不登校、引きこもりなど様々な不安を抱える親子・当事者の支援事業「子育て科学アクシス」を主宰し、これまで35年間にわたり、2000組以上の家族の相談に乗ってきた小児脳科学者の成田奈緒子さんだ。2023年3月には『「発達障害」と間違われる子どもたち』を上梓している。
成田さんは、現在の子育てであることが軽んじられているために、発達障害と間違われるケースがあると指摘する。

ーー長い臨床経験で、発達障害と思われていた子どもが、実はそうではなかったということがあったそうですね。
「そうなんです。学校などで、発達障害とレッテルを貼られて相談に来る方がいるのですが、生活習慣を変えると、症状がなくなったということが経験上多くあります」
ーー生活習慣ですか?そんなことで変わるんですか?
「生活習慣は、皆さんが思っている以上にとても重要なんです。そんなことわかっていると思われるかもしれませんが、昔に比べると、良い生活習慣は相対的に軽視されていて、そのことが今の子どもの不調につながっていることが多いです。
実際、生活習慣を作り直していくと、多くの子どもは心や身体の健康度が上がり、自律神経のバランスが良くなっていきます。すると、発達障害のような症状だけに限らない問題、例えば、学校に行けなかった子が朝から学校に行けるようになったり、学習効果が上がったり、不調が改善された事例は枚挙にいとまがありません」
成田奈緒子さんはこれまで延べ1万人以上の様々な悩みを抱える親子や子どもたちの相談に乗ってきた。そして、繰り返し「生活習慣の重要性」を説いてきたという。中学生以上の子どもでも、実践によって変化がもたらせされたことが多くあったという。
ともすると魔法のようにも聞こえる「生活習慣」だが、子どもが不調から抜け出すために何をしろというのだろうか?