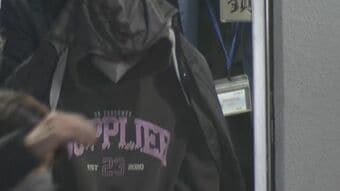誰もの進路に影響した3.11 私は…“震災枠”?
これからの進路を決めようとしていた10代の時に、災害の当事者となった私たち。
震災当時、一緒に津波から逃げた友人は地元の小学校の教師になった。学校では津波を想定した訓練を自ら行い、震災後に生まれた子どもたちに当時の体験を語ることもあるのだという。
目の前で父親が津波に飲まれていった後輩は、消防士になった。当時、助けられなかった多くの人たちを今度こそ救いたいという思いが、進路を決めた理由だったという。
そして、私自身は震災がきっかけで記者を志した。
テレビ局への就職が決まったのは震災からまだ3年しか経っていない時だった。
周囲には「採用されたのって“震災枠”じゃない?」と言ってくる人もいた。“被災したこと”が自分の価値だと思われているのだろうか、と心無い言葉に辛く悔しくなった。だが、それを糧にするしかないと思った。
熊本地震や西日本豪雨など災害現場の取材にあたったときには、どうしても3.11のことを思い出した。土砂崩れで小学生の息子を亡くした男性が現場で、泥まみれになってしまった家族写真を見せてくれたとき、固まってしまい何も聞けなかったこともあった。当時の感情がフラッシュバックするようだった。

それでも入社以来、ずっと震災に関わる取材を続けた。それは地元のためにと奮闘する友人たちや、当時、自分よりも遥かに壮絶な体験をし、生きてきた人たちの背中を押したいという思いからだった。
しかし、震災から12年が経つ今、改めて、その取材の難しさを感じている。
当たり前に笑う姿を、伝えられているのか
今年1月、10代~20代の若者が被災経験などを語る会で、話を聞いた。会では報道についてこんな声があがっていた。
「年々、東日本大震災に関する報道が減ってしまうことには疑問を感じる。でも自分が語るのはおこがましいし、必要ないかなと思う」
「伝えることは大事だが、大勢の人やメディアには語りたくない」
「助かった命がある一方で、地元では今も助けられなかった命に向き合っている人がいる。だから当時のことを語るのには今も抵抗がある」
どの言葉も、身に染みた。伝えたい思いや考えがある人は、自身の言葉で、限られた人たちに発信することができる時代だ。メディアに不信感を抱いている人もいるだろう。
一方で、震災当時、高校2年生だった男性は「12年という年月を経て気持ちに変化があった」と話した。
「震災当時、自分は“家族を亡くした可哀想な高校生”と思われるのが嫌だった。だから、取材も全て断っていた。でも、大人になって結婚し、父親となった今、当時のことに向き合いたいと思っている。これを伝えないままでいいのか、話したいという思いがある」
自分自身、取材をしていて分からなくなることがある。
自分は被災者なのか、被災者ではないのか。取材者なのか、それとも当事者なのか。話を聞かせてくれる人たちの心に、寄り添えているのだろうか。
家族や故郷を失った人たちは決して震災のことを忘れることはない、忘れられない。けれど、毎日あの日のことを考え続けているわけではない。当たり前に笑う、そんな機微を伝えていくことが、メディアには、自分にはできているのだろか。