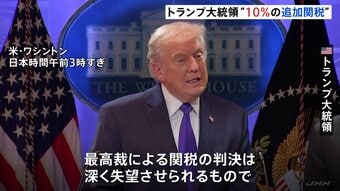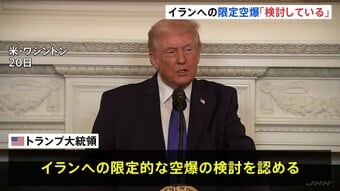政府は、新型コロナウイルスの感染症法の位置付けを大型連休明けの5月8日から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げることを27日、決定した。
コロナ政策の大きな転換点。新型コロナが世界的に流行し、“マスク生活”が日常となって実に3年が経過している。
なぜ大型連休明けの移行となったのか?そして、“マスクなしの生活”にはいつ戻るのか?総理の決断に迫った。
「引き下げられる時が来たんじゃないか」
「総理は、コロナ政策に対しては特に“慎重”だ」
総理周辺は、はっきりと語った。
2021年秋、新型コロナの感染拡大に歯止めがかからず、結果的に総理の座を譲ることとなった菅前総理。岸田総理は、前政権の後手対応を“反面教師”に、総理に就任するやいなや、当時猛威を振るい始めたオミクロン株への対応として、水際措置の強化を打ち出した。
この慎重姿勢は功を奏し、政権としての“成功体験”となった。
あれから約1年後。総理官邸では、新型コロナの分類見直しに向けた議論が本格化していった。
「分類移行について、総理と本格的に考え始めたのは、去年12月です」。官邸幹部はこのように明かす。昨秋からの感染第八波の波は大きく、過去最多の死者数にのぼっている。さらに、12月には、中国での感染が急拡大。水際措置も一層強化することとなった。
ここでも、総理は“慎重さ”を重んじた。
「年末年始の動きの結果を注視する必要がある」
総理は周辺に、感染動向の詳細な分析を指示。厚労省の官僚らは、ほぼ毎日、報告のために官邸を行き来した。減少傾向が顕著となった1月半ば、ようやく周辺にこう言ったという。
「引き下げられる時が来たんじゃないか」
そして、1月20日、「今年春」に5類へ移行することを表明した。