小学生の息子が用意してくれた「冷たいご飯」
疲労困憊し「このまま死んでしまえば、どんなに楽だろう」とさえ思った。しかし、お父さんを殺された子どもたちを遺してはいけない。その一心でかろうじて日々を生きていた。
そんなある夜のことだった。
弁護士との打ち合わせなどで遅くに帰宅すると、テーブルの上に、小学生だった息子が用意してくれた夕食があった。
冷え切ったご飯には、母親が早く食べられるようにと、お箸が突き刺さっていた。
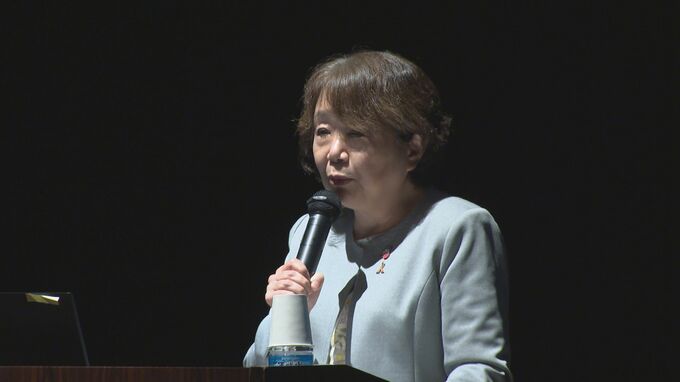
「誰かが温かいご飯を届けてくれたら」「誰かが家事を手伝ってくれたら……」
冷たいご飯とビールを一人で流し込む時、どうしようもない孤独感が胸を締め付けた。
小学生の息子は、「お父さんにとって、僕は悪い子じゃなかったかな」と言い、なぜか毎日トイレを掃除した。
中学生の娘は、誕生日に大好きなケーキも食べなくなった。それまでは皿まで食べそうな勢いだったのに。
ただただ、「お父さんに帰ってきてほしい」それだけだった。














