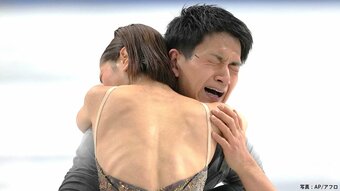「今日は署名しないから無駄」自死2日前に特捜部の取り調べ
東京地検特捜部の粂原研二は、新井が命を絶つ2日前、1998年2月17日の夕方、東京・千代田区一番町の「ダイヤモンドホテル」のスイートルームで取り調べを行った。このホテルは新井自身が指定したもので、弁護人で元検事の猪狩俊郎(33期)が構える一番町綜合法律事務所から、徒歩5分ほどの場所にあった。
粂原は前年の1997年4月、SEC(証券取引等監視委員会)から特捜部に復帰した直後、主任検事の井内顕策(30期)からこう告げられていた。
「政界ルート捜査の特命班をやってもらう」
SEC出向時代の経験から金融・証券取引事件に通じていたことが、その理由だった。
この日の取り調べで新井は、粂原に対しこう述べた。
「検事さん、調書を作っても、今日は署名しませんから、無駄ですよ。今後も取り調べには応じますから、そんなに急がなくてもいいでしょう。いつでも呼んでください」
こう言われた粂原は、3時間で取り調べを切り上げ、新井を帰宅させた。
「新井はこちらが聞いてもいないのに、出自や経歴などをかなり雄弁に語っていた。逮捕してからじっくり調べるつもりだったので、3時間ほどで帰ってもらったと思う。ただ、検察庁で待っていた主任検事の井内顕策さん(30期)から『もう帰したのか』と言われたことを覚えている」
さらに粂原は、当時をこう振り返る。
「自ら命を絶つようなことを考えている様子は全く見られなかったし、そのような事態に至ることを予見させる言動もまったくなかった」
この日の取り調べで、新井は「日興証券に儲けさせてもらった事実」は認めたが、「利益提供を自分から要求したことはない」と従来の主張を繰り返した。さらに、新井は供述調書の作成自体を拒否した。
特捜部の狙いは、新井に「否認する調書」に署名させることで、後に本人の「虚偽」を立証するために、証拠として確保することだった。しかし、新井はこれも一切拒否し、最後まで応じなかったのである。
関係者によれば、新井は「しばらく任意の取り調べが続くだろう」と考えていたという。だが特捜部は、「在宅のまま任意捜査を続けても新井が真実を語るとは考えにくい。さらに証拠隠滅の恐れもある」と判断した。最終的に「任意捜査」から「強制捜査」に切り替え、逮捕に踏み切る方針を固めていた。
通常、国会議員の取り調べは東京地検特捜部副部長の役割とされている。これは「国民に選ばれた議員への敬意」を示す意味があった。
1976年のロッキード事件で田中角栄元首相を取り調べたのは副部長の石黒久𥇍(8期)。その後も、1990年代に金丸信元副総裁や中村喜四郎元建設大臣、阿部文男元長官らを担当したのはいずれも当時の副部長、熊﨑勝彦(24期)であった。
1995年の二信組事件での山口敏夫元労働大臣は有田知徳(26期)、2000年の石橋産業事件での中尾栄一元建設相は井内顕策(30期)、2002年の鈴木宗男議員は谷川恒太(32期)と、国会議員案件は副部長が直接当たるのが慣例だった。
この慣例に従えば、新井の取り調べを担当するのは副部長の山本修三が順当であった。しかし、SECへの2年半の出向経験があり、証券事件に精通していた粂原を「適任」と見た山本は、あえて任務を託したのである。