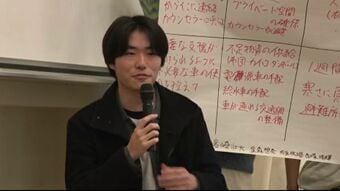方言の記録は、地域の自然環境や文化、人々の暮らしの記録
ほかにも、川魚にはさまざまな方言名がある。MROラジオで方言の話題を発信している金沢大学の加藤和夫名誉教授(福井県越前市出身)の子ども時代に使っていた方言名には次のようなものがあった(方言名の後ろの括弧内が標準和名)。
● ドバ(アブラハヤ)
● マルタ(マルタ、マルタウグイ)
● サクラ(ウグイ)
● キンタン(タナゴ)
川魚の方言もまた、地域の自然と文化、そして人々の生活と密接に結びついてきた。特に子どもたちの世界で育まれてきたメダカの方言の豊かさは、日本の言語文化の多様性を象徴している。「ザコッコ」「ジャコバイ」「ウキメンコ」「タイチンボ」――。こうした方言の響きの中に、かつての子どもたちの小川や田んぼで遊んだ記憶が刻まれている。
しかし、環境の変化により野生のメダカが減少し、子どもたちの遊び方も変わってきた現代では、こうした言葉の多様性は急速に失われつつある。方言の記録は、単なる言葉の収集にとどまらず、地域の自然環境や文化、人々の暮らしの記録でもあるのだ。
【参考文献】 辛川十歩・柴田武(1980)『メダカの方言―5000の変種とその分布』未央社
加藤和夫
福井県生まれ。言語学者。金沢大学名誉教授。北陸の方言について長年研究。MROラジオ あさダッシュ!内コーナー「ねたのたね」で、方言や日本語に関する様々な話題を発信している。
※MROラジオ「あさダッシュ!」コーナー「ねたのたね」より再構成