二世、三世も含めた「戦後世代の語り部」の役割
首都圏中国帰国者支援・交流センターが養成した「中国残留邦人等の体験と労苦を伝える戦後世代の語り部」は現在13人。
なかには帰国した人の二世、三世もいます。
今村さんは、二世、三世が自分の家族のことを語るような迫力は出せないので、聞き取った当時の情景を絵にして伝えることにしたそうです。
「中国残留邦人等の体験と労苦を伝える戦後世代の語り部」今村幸一さん
「高校生とか大学生の方がお話を聞いていただくと、絵が印象に残りました、というお声を聞くので、描いてよかったかなとは思っています。
逆に、大学生の方でも残留邦人のことをご存知なくて、話を聞いて、びっくりしましたという反応もあります。
やはり、若い人たちによりお話を聞いていただきたいなという希望はありますね」。

「いわつき ともちゃんの会」が開いたこの集まりには40人近い参加者が、話に聞き入りました。
隣に暮らす中国帰国者(残留孤児、残留婦人)の記憶をつなぐ意味
岩槻の小学校で、同級生に残留孤児、婦人の二世、三世がいたという在日コリアン三世の男性は「小学校5、6年生の時、先生が実は残留孤児の話をしてくれたんです。今の学校でこういう話をどこまでしてるんだろうと。こういう話をどんどんどんどん、ここの小・中学校の人にしてほしいなときょうは思いました。それぐらい、すごくなんかちゃんと記憶を残さなきゃいけないと思いました」と感想を話しました。
また、インターネットで「ともちゃん地蔵」のことを知り、京都府から来たという、残留婦人三世の女性は「残留婦人について、もうあんまり知らない方が多い。
つらい経験をされた方のことを、私自身も三世として、すごい残していきたいっていう思いがあるので、もっといろいろ情報を集めて知りたいなっていう思いできょうは参加させていただきました」と話しました。
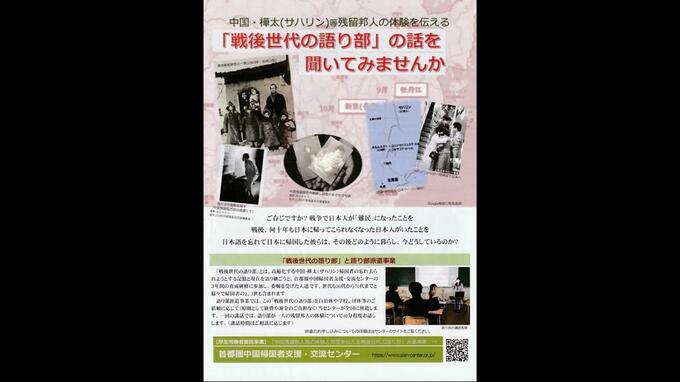
岩槻だけでなく、全国各地、中国から帰国した残留孤児、残留婦人は、現在も私たちの隣に暮らしています。
一世だけでなく、二世も高齢化していて、日々の暮らしで地域から孤立したり、医療や介護の場での課題に直面しています。
首都圏中国帰国者支援・交流センターが派遣する「戦後世代の語り部」の話から学べることは多いでしょう。
若い世代が記憶を受け継いでいく必要性をあらためて感じる取材でした。
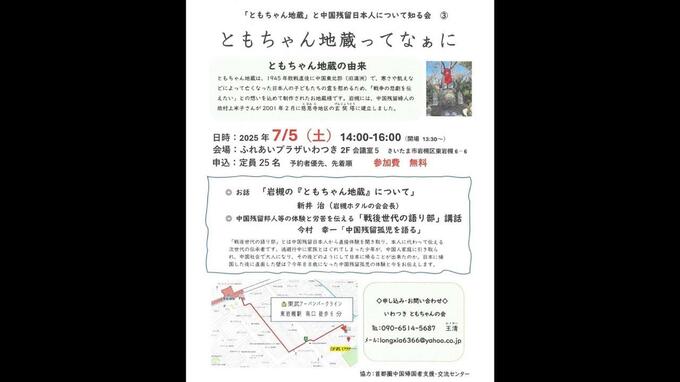
(TBSラジオ「人権TODAY」 担当:崎山敏也)














