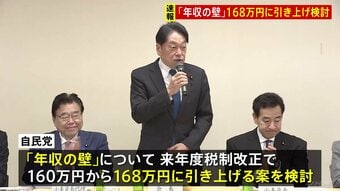2021年秋の衆議院解散で政界を退いた菅野志桜里前衆院議員。(議員時代は“山尾志桜里”で活動)2016年に「保育園落ちた日本死ね!!!」と題したブログを国会で取り上げ、待機児童問題の解決を訴えたことなどで脚光を浴びます。一方で、不倫疑惑や議員パスの不適切使用などの週刊誌報道が相次いだことでも世間から注目されました。
なぜ政治家を辞めるという決断に至ったのか。背景にある「新人時代は“雑巾がけ”」「“バス旅行”が政策論スキップする」・・・政界から距離を置くからこそ指摘できる日本政治の違和感を聞きました。
なぜ政治家を辞めるという決断に至ったのか。背景にある「新人時代は“雑巾がけ”」「“バス旅行”が政策論スキップする」・・・政界から距離を置くからこそ指摘できる日本政治の違和感を聞きました。

■「自分の仕事、頭打ちかな」このままだと「永田町で錆びる」
ーー政治家を10年で辞めるという決断をした背景には何があったのでしょうか?
政治の世界の外に出た方が社会の役に立てるかも、自分も成長できるかも、という感覚が最大の決め手だったと思います。
私は、議員になる前は検事だったのですが、辞めて議員になって12年。落選の期間が2年あったので、のべで言うと10年です。あと数か月で任期満了か解散だよねっていう時になって「次の選挙出るの?私」って考えたんです。それで、仮に当選できたとして議員を続けても、「自分の仕事、頭打ちかな」っていう感じがしたんです。
ーーどういうところを「頭打ち」と感じたのですか?
まず、一議員としては、質問をして、「そういう問題があるんだ」ということを社会に伝えていくことが役割だったと思っています。保育園の待機児童問題の時や検察庁法改正案の時には、私の問題提起をきっかけにハッシュタグをつけてツイートしてくれたり、署名サイトで署名してくれたりする動きが広がりました。永田町の“中”と“外”で「化学反応」を起こしながら、物事を動かしていくっていう“一つのスタイル”が、出来上がったような気がするんです。
もし政治家を続けていたら、同じようなことはできたと思います。でも、一つのスタイルがすでに出来たのだから、あとは色んな議員がそれぞれのテーマでこのスタイルでやっていったらいいよね、という感覚になりました。
もう一つは、政治家は続けないと上には行けないの?っていう感覚もありました。当選し続けて、政治家として生き残り続けることで「上が抜けるのを待つ」という現状への疑問です。
そうやって自分が活躍できる時を待って頑張っている若手もいっぱいいます。でも私にはそれができないと思ったんです。待っているうちに、自分の成長は永田町の中で止まり、むしろ錆びていくような感じがしました。
だったら政治家として時を待つより、一旦外に出て、今度は“外”と“中”をどう「化学反応」させるかということを「別の立場」でやってみたいなっていう気がしました。
やっぱり10年ひと区切りで次に行くという“入れ替わり”が、どんな世界でもすごく必要だと感じています。