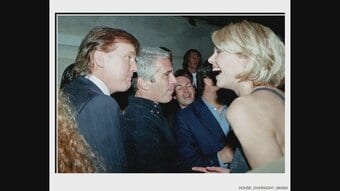■「一生骨をうずめて当たり前」では政治家になる人は増えない
ーー政治の世界も“入れ替わり”が必要ということですか?そう思います。政治家って一旦辞めると終わり、みたいなイメージがありますよね。「選挙に落ちたらただの人」というか。謎の感覚なんですけど。そんな現状のなかで政治も「出入り自由なんだ」っていうことが当たり前になっていくきっかけに少しでもなったらという気持ちがあります。
私は2007年に検事を辞めて、それまで縁のなかった選挙区から出馬しました。いろいろ勉強になったんですけど、やっぱり知らないとこから来たので、(地元の人に)「一生、ここに骨をうずめるんですか?」と聞かれて、すごく辛かったです。その時は「はい」と答えていたんですが、「自分は本当のこと言ってるのかな」っていう感覚があったからです。
この「一生骨をうずめて当たり前」というキャリア設定だと、政治家になる人はすごく少なくて、ハードルが高いと思います。特に女性にはハードル高いんじゃないかなという気がしました。

ーー地元の人からすれば、自分たちの代表に本当になってくれるのかなという不安があるのもわかる気がします。
もちろん骨をうずめる政治家を否定するものではありませんし、地元の人の不安もわかります。ただ、政治家を辞めない人が多いことが、新しい人が入れない状況につながっているし、辞められない文化が、魅力的な人が入ってくるのを阻んでいる側面もあると思うのです。ですので、続けるべき、出入りすべき、ではなく「出入りもありなんだ」という感覚だと思っています。
ーー“出入り自由”のキャリア設定だと、新人からすぐさま仕事ができる環境がないといけないですね。
そこも課題です。私が力不足だったからかもしれないけど、「1期生の仕事は2期目当選することだ」って言われて、「国会にいないで、地元回れ回れ」と言われて。国会にいても、むしろ質問とかに立つってよりは“雑巾がけだ”といった感じでした。例えば、国会対策委員長の部屋に行って、新聞記事を切り取ってコピーしろと言われるわけです。そういう政治文化の中に新規参入って非現実的です。
1期生だって、新聞の切り抜きのために歳費をもらってるわけではないです。次の選挙に受かるために、盆踊りを一緒に踊るために歳費をもらっているわけでもないです。やっぱり「一期目からちゃんと仕事ができるのが当たり前」となる必要があると思っています。
ーー確かに盆踊りに行くと政治家がいて一緒に踊ってますよね。それっていらないんでしょうか?
有権者と距離を縮める活動っていうと、盆踊りだけでなく、駅で喋って握手をして、自らチラシを配って、政治家も普通の人なんだって思ってもらう。私もそういう選挙活動をやってきました。次の選挙で当選するために、イベントで触れ合うことをやっているわけです。
触れ合うことで距離を縮めることが、100パーセントいらないとは言いません。でも、これって本当に民主主義を良くしているのかなと10年活動して思ったんです。距離を縮める努力をすればするほど、人間関係で票をとるようになっていって、政策の話が届かなくなっていくっていうジレンマがあったんです。
ーー具体的に、どういうことですか?
触れ合いによって、家族的な信頼関係を築き、有権者と繋がっていくことは、有権者の人たちが、自分たちの暮らしに何が必要かとか、政治家には何を求めたらいいのかっていうことを一緒に考える機会をスキップしてしまうような感じがしたんです。
だから私は議員だった最後の数年間は「一緒にバス旅行行きましょう」とか「お餅をついて食べましょう」とか、地元の方との「触れ合い」は基本やめました。「大事な一票を託してもらった分、仕事は一生懸命やって、それを伝えます」というスタイルに変えてみたんです。「政治のプロ」として仕事を託してもらうんだという形に変えていきました。