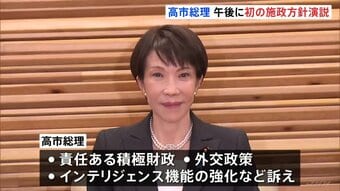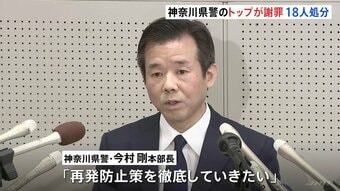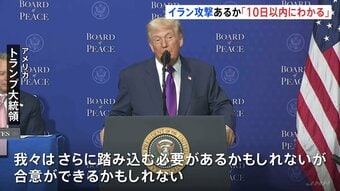危機に瀕する土壌
「15秒でサッカーコート1面分の肥沃な土が失われている」と藤井さんは警鐘を鳴らします。このペースは1年間で岩手県の面積にあたります。土壌が劣化し、植物が育たなくなる原因は、過剰な農業利用や地下水のくみ上げによる塩害、戦争による被害です。
その一方で、アマゾンでは年間で岩手県の面積にあたる熱帯雨林を切り開かれ、農地として開発されてます。「これはもったいない状況。今ある畑を上手に使いながら熱帯雨林を守った方がいい」と藤井さんは懸念を示します。ちなみに、岩手県の面積は東京、埼玉、神奈川、千葉の合計面積を上回ります。
土壌は植物や微生物が膨大な時間をかけて作っていきます。「北海道では1万年前の地面が1メートル下にあることから計算すると、1センチの土が形成されるのに100年かかっています。日本は火山の噴火や土砂崩れがあるから早い方で、アフリカでは1センチに1000年かかります」と藤井さんは説明します。
一方で、人間の活動による土壌の消失は自然に作られる速度をはるかに上回ります。「私たちが土を耕すと、10年で1センチほど風や雨で失われてしまう。つまり、土に関して私たちはずっと『赤字』なのです」
土の生産性を維持するため、現在私たちが頼っているのは化学肥料です。化学肥料というイノベーションにより、世界人口は80億人まで急増しました。しかし藤井さんは「化学肥料がなければ今の世界人口を支える生産性を維持できなくなった。リスクも巨大化している」とも指摘します。
また、藤井さんは有限な資源に頼る化学肥料について、「あまり持続的ではない側面もある」とも語ります。化学肥料に含まれる栄養であるリンは海鳥の糞やクジラなど哺乳類の化石から、カリウムは古代の海の塩から、窒素は化石燃料を使って大気から固定しています。「つまり、現代の農業は太古の時代に生きていた生物から資源を借りて成り立っているのです」