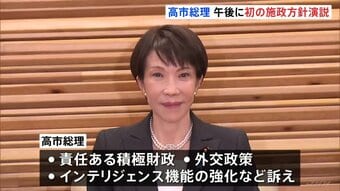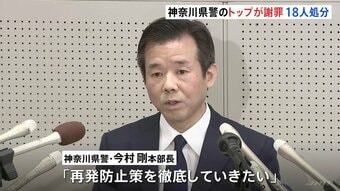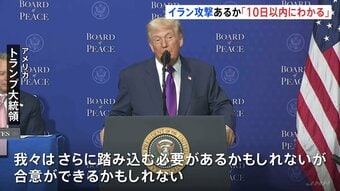「土」は日常生活に密接にかかわりながら、重要性が見過ごされがちな存在です。口にする食べ物、特に最近値上がりが話題になっているお米も、土がなければ育てることはできません。
しかし今、この「土」が戦争や気候変動の影響によって失われつつあり、1年で岩手県分の面積が消えているといいます。カナダ極北の永久凍土からインドネシアの熱帯雨林まで、スコップを片手に世界各地を飛び回る土壌学者・藤井一至さん(福島国際研究教育機構・土壌ホメオスタシス研究ユニットリーダー)に聞きました。
(TBSラジオ「荻上チキ・Session」2025年5月19日放送分から抜粋、構成=菅谷優駿)
「土」とは何か カギは生命活動
「ざっくり言って、世界には12種類の土があります」と藤井さん。日本で見かける土は黒や焦げ茶色をしているイメージですが、アフリカなら赤、東南アジアだったら黄、北欧は白…と、世界各地で典型的な土の色も変わってきます。日本の土はお米を育てるのに適しているけど、小麦粉には向いていない…とそれぞれ適性があるそうです。
何が違いを生むのか。藤井さんは「気候や生えている植物、地形、火山灰や花崗岩といった材料、そしてアフリカだったら何億年、日本だったら1万年ぐらいしか経ってないという時間。この5つの要因が土の種類を決めています。その要因が違えば全然違う土になるし、同じ条件だったら同じ土になる」と語ります。
では、そもそも「土」って何なのでしょうか。藤井さんは「土とは、岩石や火山灰が風化してできる砂と粘土といった鉱物と、動植物が微生物に分解されてできる『腐植』が混ざったもの」と説明します。重要なのは「生命活動」があるかどうかだといいます。「月や火星にも砂はありますが、生き物と生き物でないものの相互作用がないと『土』とは言えません」
地中を研究する分野といえば、地質学が思い浮かびます。土壌学と地質学の違いについて、藤井さんはこう説明します。「地質学は地層、土壌学は土と、それぞれ研究対象が違います。地層は化石など昔の生き物を閉じ込めていて変化しないものですが、土は植物や微生物と砂や粘土が交わり合いながら、環境を反映して今まさに変化しているものなのです」