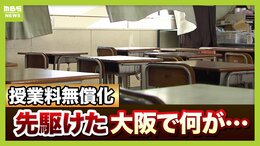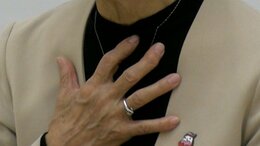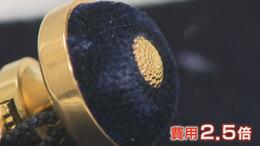日本で死刑制度 情報開示と議論の場を
先進国の中で、死刑を行う数少ない国である日本。十分な情報開示が行われているのか。
裁判員裁判で死刑判決を出した米澤敏靖さんは、「死刑の実態を知らされていない自分が、極刑の判断を迫られたのは不当だ」と感じている。

米澤敏靖さん(37)
「情報開示などをオープンにした上で(死刑)判断に関わるのはいいかなと思います。今の状態では、私は二度と関わりたくないです」
米澤さんが裁判員を務めたのは、2009年に川崎市のアパートで、津田寿美年元死刑囚が大家の男性ら3人を殺害した事件。
津田元死刑囚は、一審の裁判員裁判で死刑判決を受けた。

米澤敏靖さん(当時22)
「自分たちの選んだ判決で、この人は亡くなってしまうんだと思って、辛い気持ちでした」
津田元死刑囚は、その後、自ら出した控訴を取り下げ死刑が確定した。
米澤さんは、十分な情報や知識がないまま結論を出した死刑で、刑が執行されることに怯えてきたという。
2014年、死刑についての情報開示が進むまで執行停止を求める要請書を作成し、別の事件で裁判員を務めた仲間たちとともに法務省に提出した。

しかし、法務省は1年10か月後の2015年12月、裁判員が判断した死刑では初めてとなる津田元死刑囚の刑を執行した。
それから10年、死刑についての情報開示は進んだのか。
米澤敏靖さん(37)
「(情報開示は)正直10年前と何も今変わってないような状況。もう少しというか、本当に真剣に考えて欲しい」
米澤さんらは、裁判員制度がスタートして15年となった節目の2024年、死刑について国民的議論を促すよう求める新たな要請書を法務省に提出した。
その中では、情報開示が進むアメリカを例に挙げている。
米澤敏靖さん(37)
「アメリカは全部オープンにするような国だと思うので、どこまで必要かは議論していく中で決めていけばいいと思うので、まずはその議論の場を作っていただきたい」
「死刑の実態を知らなければ正しい議論はできない」。それが米澤さんの思いだ。

米澤敏靖さん(37)
「クローズド空間で(死刑を)やっているという印象を受けます。今の(死刑)制度については。(裁判員に)重い責任を負わせるのであれば、知る権利もあると思うので、きっちりしていただきたい。まずは議論してみようというのが率直なところですね」