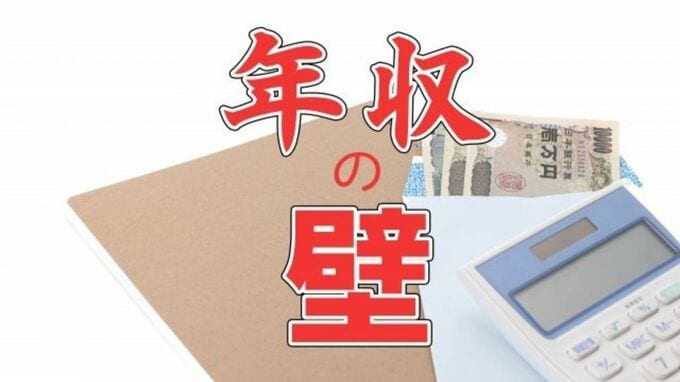国会は来週召集され、総理大臣指名選挙が行われる。石破内閣の本格始動だが、衆院選で与党は過半数の議席を取れず、政権運営は波乱含みだ。そんな中、カギを握ると言われるのが、大躍進した国民民主党が主張している「103万円の壁」の見直しと、「トリガー条項」の凍結解除という二つの政策を、与党がどこまで飲むかどうかだ。元サンデー毎日編集長・潟永秀一郎さんが11月8日、RKBラジオ『立川生志 金サイト』で解説した。
少数与党内閣が国民民主に「部分連合」求める理由
「103万円の壁」と「トリガー条項」。どちらもこれまで聞いたことはあっても、じゃあどういうことかとなると、ちょっと答えに詰まってしまいますよね。そこで今日はあらためて、その意味と課題などについて説明します。
その前にまず、国民民主がカギを握るに至った今の政治状況から、おさらいします。10月の衆院選で自民党は56減らして191議席、公明党も8減の24議席、計215議席で過半数の233を割り込みました。
その後、裏金問題で離党勧告を受けた世耕さんや、公認されなかった萩生田さんら計6人が自民会派に加わりましたが、まだ12議席足りません。首相指名選挙は決選投票で石破首相となる見込みですが、野党の協力を得なければ予算も法案も通らない、少数与党内閣になります。
そこで与党が模索しているのが、衆院選で4倍増の28議席を獲得した国民民主との連携です。もともと憲法改正や防衛力強化に肯定的で、大企業の労働組合を主な支持母体とする国民民主とは政策的にも通じるところが多く、政策ごとの「部分連合」を求めて協議が始まりました。
その際、国民民主の玉木代表が協力の絶対条件としたのが、「年収103万円の壁」の引き上げ実現です。また、国民民主は以前、ガソリン税を軽減する「トリガー条項」の凍結解除を条件に予算案に賛成したものの、反故(ほご)にされた恨みがあるので、この実現にもこだわっています。玉木代表は「今回は食い逃げは許さない」と強気ですから、自民党もゼロ回答はできず、内部で検討が始まっています。と、ここまでが今に至る状況でした。
税収減を伴う「103万円の壁」引き上げ
では、本題の二つの政策について。まずは「103万円の壁」の引き上げから説明します。
「103万円」は、税金を算定する際に年収から差し引かれるベースの金額です。「基礎控除」と呼ばれ、年収がこの額を超えると所得税がかかり始めます。国民民主党は、これを178万円まで引き上げるよう求めています。
それが何をもたらすか。引き上げには、二つの目的があります。一つは「減税」です。税金がかかる収入を課税所得と言いますが、あらかじめ収入から差し引かれる控除額が引き上げられれば、その分、課税所得は減って、そこにかかる税金も減ります。
一番わかりやすいのは年収178万円の人で、今はおよそ4万円の税金がかかるのがゼロになります。納税するほぼすべての人に恩恵があり、物価高のなか、ありがたい話です。
半面、税収が減って財政が厳しくなるという“副作用”もあります。政府は基礎控除を178万円に引き上げた場合、税収はおよそ7兆6,000億円減り、そのうちおよそ4兆円が地方税だと試算しています。
ただでさえ社会保障や少子化対策、防衛強化などで歳出が増える中、その手当てをどうするのか。特に影響が大きい地方自治体の税収減をどう補填するのか、大きな課題です。ただ、減税によって手取りが増えれば、一部は消費に回るなど経済効果も見込まれ、政府の試算はそのプラス効果を反映しない単純計算でもあります。
また、基礎控除が上がると所得が多い人ほど減税額も大きくなる、という指摘もあります。毎日新聞が報じていますが、大和総研の試算によると、年間の減税額は年収200万円の人でおよそ9万円なのに対し、年収500万円でおよそ13万円、年収800万から1000万円ではおよそ22万円と増えていきます。
ただ、今の納税額からの減少率は年収200万円だとおよそ95%、500万円で35%、1000万円だと16%と、低所得者のほうが大きいので、高所得者に手厚いという指摘は必ずしも当たらないと、玉木代表は反論しています。
とはいえ、財政再建を至上命題とする財務省の抵抗は強く、自民党も財務省を政策ブレーンとしていますから、落としどころを探っているのが現状です。早くも財務省側からは「抜本的な制度改正は、年度内には間に合わない」との声があり、当面は年末調整で相応の額を割り戻し、来年度中に財源問題も含めた制度設計をして、本格実施は再来年度にする案も浮上しています。