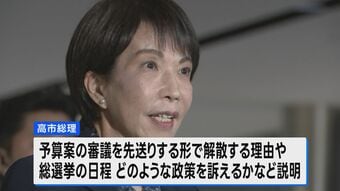「頼れる人がいない」若者の苦悩 背景に
30代の女性BさんはLINEの安否確認サービスに加入した一人。
東京に出てきて15年以上、賃貸アパートに1人暮らし。小さな会社を転々としているうちに「もしここで死んだら?」と考えるようになった。

Bさん
「婚活もしてきましたが、30歳を超えたとき結婚を諦めました。自分が人の面倒を見るのは構わないのですが、人に自分のことをお願いするのが苦手。父親が脳梗塞をして母親が苦労しているのを見たのも、後のことはきちんとしようと考えたきっかけです」
毎朝送られてくる、LINEの安否確認サービスにOKを押す。
それだけではなく、万が一の時に備えて、生命保険の証券や公共料金の引き落とし、銀行口座と連絡先を記したファイルも用意した。
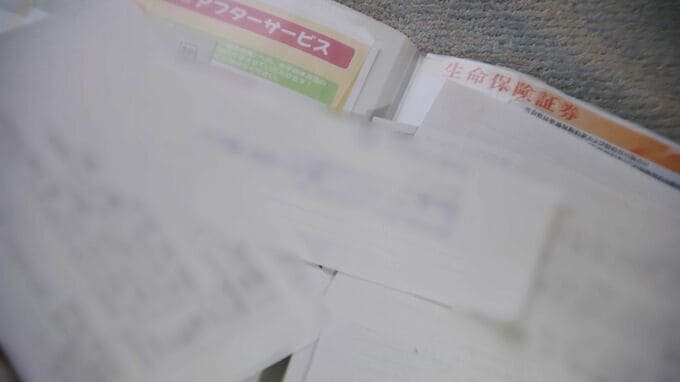
Bさん
「このアパートの住民も回覧板は回ってきますが、顔も名前も知りません。会社の同僚とも、深くプライベートなことまで関わろうとはしなくなりました。ネット社会が進んで、その気軽さを楽しむ一方で若い人が孤独死で亡くなるのをニュースなどで知ると“ああ、こういう時代になったのかな“という思いはあります」
この4月から、社会から孤立していることにより心身に有害な影響を受ける状態になるのを防ぐことを目的とした「孤独・孤立対策推進法」が施行され、自治体には支援団体で構成する地域協議会を設置する努力義務が課された。
だが、孤独死を防ぐ活動をしている紺野さんはこう訴える。
紺野さん
「この5年でデジタル庁もできてデジタル化が進み、お年寄りにスマホの使い方などを伝える活動は大変やりやすくなりました。一方で、地方自治体などを回ると孤独・孤立対策推進法のために具体的に何に取り組むか、方針を立てているというところはほとんどありません」
「ニーズはすごく高いと思います。お年寄りだけでなく、若者たちからも “ネットでの繋がりはあっても、困ったときに頼れる人がいない”という 声をたくさん聞きます。コロナ禍の“ステイホーム”は、そういう人間関係を浮き彫りにしました。それだけで何とかなるという問題ではないですが、行政には早く有効な施策を打ち出してほしいと感じます」
「報道特集」では、若者の労働環境や生き辛さをテーマに取材をしたいと考えています。情報提供は番組ホームページまでお願いします。